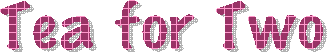|
|
―二人でお茶を―
第三話
|
その後、私たちはこの店を三十分で辞した。食べるものだけ食べて、ちょっとお茶を飲んで、それ以外に何と言うか、身じろぎ一つとれなかった。多分カヅユキは、こんなわけでフィアンセがいるから別れてくれ、と話したかったらしいのだが全くできず、私は、どうふるまっていいのかわからず、嫌な感じの緊張が続いた挙げ句、彼女はこんなことであきらめたりしないから、ととても強気な意見を述べると伝票をひっつかんでつかつかとレジに向かってしまったのだった。素人にはつらい量のアイスクリームを食べさせたような形になってしまった私は、それで払わせるなんて悪いことをしたなぁと思いながら、それでも何ができると言うわけでもなく、カヅユキと連れ立ってとりあえず店を出た。 「ひなちゃん、もう少し話し合わせてよ」 カヅユキは、本当に何にも考えていない様子で言った。何が、もう少し話を合わせろ、だ。思った私は傍らの彼の足を思いきり踏んづけた。 「いってーっ。何すんだよ!」 「何すんだよ、じゃないでしょ?そういう科白は合わせる話を作ってきて、打ち合わせをしてから言うものよ」 「そ……そんなこと言ったって、あ、あんなに修羅場ちっくになるなんてさぁ……」 とほほ、と言いたげな口振りでカヅユキが言い訳をし始める。あーあ、どうしてこんな頼みを聞いたりしたんだ、私は。自分の人の良さ加減に私自身もあきれて、できるのはひたすらため息だけ。たかが三十分ほどお茶をしただけだと言うのに、異様に私は疲れていた。当たり前か。緊張の連続でいつものパフェも全然おいしくもなかったし。こっちがとほほ、とか言いたくなるわよ。カヅユキはしかし自分の問題でいっぱいいっぱいらしく、これからどうしようか、どうしよう、とか一人でぶつぶつ言い始め、疲れた私を労ったり、お詫びにご飯をおごってくれたり、そういう気の回し方というのは全くできなさげだった。この男にアフターケアなんてものを望んではいけないわ、と私は思い直し、じゃあ今度はフレンチよ、と言って帰ることにした。したのだが。 「そんな無責任な!まだなんにも解決してないよ?」 「それは私が解決しなきゃならないことじゃないと思うわよ?」 「でででででも、オレ一人でどうしろって言うんだよぅ?」 「あんたもう子供じゃないんだから、一人でなんとかしなさいよ!」 「子供じゃないから話がややこしくなってるんだろ?長いつきあいじゃん、オレ達。協力してよ。ね?」 歩き出す私にカヅユキがすがってくる。振り切って、私は必死に先へと進む。 「ひなちゃーん……一生のお願いだよぅ」 「いやっ、いやったら絶対にいやよ!なーんであんたの別れ話に協力なんかしなきゃいけないわけ?」 「だって俺ふられたことはあってもふったことないし……そこはやっぱり百戦錬磨のひなちゃんに……」 「誰が百戦錬磨だ、誰が!」 怒りにまかせて、街中にもかまわず、私は叫んでいた。うう、と、カヅユキは小さくうなり、そして年甲斐もなく泣きべそかくような顔で私を見た。 「な……何よ」 そういう顔をされると、何だか私がいじめているみたいじゃないの。思いながら私は後退りをする。けど言っていることは正論だわ、人の色恋沙汰に、しかも始末の悪いのにつきあわされる義理なんてないはずなのに、いやーな思いをさせられたんだから。た、確かにフレンチをおごらせる約束で……ちょっとたかったみたいな感じだったけど。やや、罪悪感あり。人の弱みにつけ込んでご飯をおごらせようというのは……確かにあんまりいいことではない。どちらかと言うと、弱みにつけ込んだ時点で悪いような……。 「……わかったわよ、協力すればいいんでしょう?」 私はここで、自分の良心の呵責(?)に負けた。ああせめて、無償で協力するってことにしておけばよかった。がっくりと、言ってしまってから私は肩を落とし、逆にカヅユキは生き返ったように生き生きとし始め、とどめににっこり笑いながら、 「ありがとう、ひなちゃん!恩に着る!一生忘れないよ!」 とこんな具合に復活してしまったのだった。あーあ。 「ふぅ……」 「ひなこさん、どうか、されたんですか?」 あーあ。最悪な事態はそれだけでは終わらなかった。一日明けて日曜。私はその人と会う約束を伯母、ゆかこさんにされ、その人と会っていたりした。そう、見合いの続き。思慮深そうな年上の眼鏡の人は、思わずため息をついた私を見て、やや心配そうに言った。私はあわてて、 「あ、いいえ。ちょっと疲れてて……何でもないですよ?」 こんな具合につくろってあはははは、と笑ったりしていた。一昨日とはうってかわって、私はいいこだった。自分のいい子加減に、変に疲れてもいた。野沢ゼンノスケ、というとても古風な響きの名前のその人は、大人しそうに見えて話のうまい人だった、見た目はー……平凡なサラリーマンそのもので、ハンサムでもなければ特別ブ男でもない。スタイルもいいかと言えばそれほどでもなく、ふつうの、ふつうの、真面目そうな印象的には「いいひと」だ、と思う。日本女性の言う「いいひと」が、どういうものかは誰でも想像がつくと思うのだけれど。「いいひと」だ。 「すみません、何だかご無理を言ったようで」 「あ……いいえ、そんなことないんですよ、そんなことは……」 ぺこりと素直に頭を下げる彼に、逆に私が恐縮してしまう。こんなやりとりをしているおかげか、彼が私に持っている印象というのは「紅茶が好きな大人しいお嬢さん」という……なかなか幻想的なものだった。文字だけ見ていると、一体どこの世界の住人かしら、と思えるけれど……彼は私の茶乱ぶりはもう知っているので、そういう部分ではリアルな感じ……どうリアルかは一口では説明できないけど。ここは和菓子と抹茶なんですが、どうですか、と、連れられてきたのは実は始めての店だった。大手着物チェーンの本社ビルに入っているそこは、何でも宇治にある高級抹茶を取り扱うお店が唯一開いている喫茶室とかで、お茶もお菓子も一級品の、結構高くつくところだった。もちろん、お茶はおいしい。一体グラム当たりいくらするんだろう、と思われる香りと口当たりは、いくら働いていても自腹ではそうもしょっちゅう口にできなさげな、すばらしいものだった。小売りもしているそうですよ、と言われて心が動くのが茶乱。けれど、買って帰ってももったいなくて飲めない気がするほど、そのお茶は高価だった。たまにあるのよね、こういうの。更に付け加えると、茶乱のくせに茶道はかじったことしかなくて、自力ではお茶を立てられなかったりもする。な、情けない。 「うあー……おいしい。よく知ってらっしゃいますね、こういうところ」 「いや……おばが教えてくれたんです。あなたが、お茶が好きだと話したら」 照れながら彼は正直に言い、僕はそういうことはからきしだめで、と苦笑を漏らす。初めてお会いしたときもおいしそうに飲んでみえましたよね、と言葉は続く。さすがは営業、相手のチェックにぬかりがない。気のきき方と言い……大人だわ。珍しいくらいのその気のきかされ方に、私はちょっとだけ気分が良くなっていた。今まで、人のいわく「とっかえひっかえ」だったけれども、こんなふうに気を使ってくれる人にめぐりあったことはなかった。そういう人は私のような感じの女の子を引っかけたりは、しないんだろうなぁ。話しやすくて、適当にあいづちを打ってくれて、適当にボケてつっこんで、ああいいな、と私を思ってくれる人は、何と言うか私の愛想の良さをいいな、と思っただけで、自分が愛想良くしてくれていたかと言うと、全部が全部そうではなかった。当たり前だけれども。 何だか私が笑うと「このコ俺に気があるのかも」と、みんな簡単に考えたりするらしい。そういう顔なんだそうだ。そこへ短絡的に駆け込まない人と言うのは珍しく……もしかしたらこれがお見合いのメリットの一つ、なのだろうか。お茶を飲んでいる間はしかし、そんなことは考えたくはなかった。おいしく飲んで、食べて、まったり。それが理想と言うか……希望よね。コーヒーを恋の味、と歌った人はいるけれど、お茶をそういう人は少ない。茶乱の誰もが到達するであろうと思われる、このまったりは、そんなに熱くも甘くも苦くもなく、もっとすがすがしい感覚だ。え?私だけ?とにかくお茶はまったりが一番。時々カフェインのためにエキサイトするけれど、やっぱり、まったりが一番。 「そうしていると、本当にしあわせそうですね」 「はい、もちろん」 相手が誰なのか全く無視して、素で私は言い放ってから、正気に戻った。にっこり、目の前で野沢さんは笑っていた。ま、まずい。変に気に入られて次の約束なんか取り付けられたら、目も当てられないわ。しかし彼はそんな私の思惑など知らず、私の前で初めて、くすくすと声を立てて笑った。 「の……野沢、さん?」 「ああ、すみません。僕、実は年下の女性と個人的に親しくすることがあまりなくて。働いていると聞いて、もっとぱりっとした方かと思ってましたから」 「は……はあ、そうですか」 いや、たかがOL五年生が、そんなにしっかりしているはずもないけれど。内心そんなつっこみを入れる私を置き去りに、野沢さんはとても機嫌よさげだった。そして、あれですね、本当に好きなものの前だと、みんなそうやって素直なんですよね、と実に楽しそうに言ってのけた。実際私は、一瞬だけれど素だったので、そのことに対しては何も言い返せなかった。洋菓子なんかはどうですか、と、そのノリで野沢さんは話題をつなぎにかかる。大好きですぅ、とか言ってしまうと今度こそ本当に、取り返しがつかないなぁと私は思いながら、答えず、一つ息をついた。 「野沢さん、あのですねぇ」 「はい」 私は、その話を切り出すことにした。切り出すことにしたが、目の前の彼は何が楽しいのか、ずっと笑っていた。さすがは営業、そういう顔はお手のものね、と、自分に言い聞かせないとうっかり負けそうなくらい、彼は笑っていた……違うかな。その手の表情に、私が弱いのかな。うう、と私は言葉に詰まった。しかし、彼は今までのとっかえひっかえした人たちとは違う。伯母が、結婚させたいが為に引き合わせた男なのだ。いつまでも断れず、なあなあとだらだらとやっていたら、私の本当の意志とは裏腹に、そういう結果に転がり込んでしまう可能性は大だった。そ、そりゃあ今までは、何と言うか、何もかもが自分たちだけという小さな単位で転がっていたわけだから、だらだらしていてなあなあつき合って危険になる前に(何がかは聞かないこと)始末もついてたわよ?何とか。十代後半から二十代前半の男の人というのはけっこうわがままで、自分のものにできないとなるやすぐに掌を返してくれたし、そうでなかった人は今やメル友もしくは茶飲みグループだし、何と言うか、始末はついてきたのだ。何とか。だからこれは、いわゆる一つの未知への冒険だった。私が私の悪いところ、曖昧な笑顔でイエスノーがはっきり言えない、それを克服するための、一つのハードルなのだ。 「あの、ですね」 「……はい?」 って、決意は良かったのに、やっぱり言葉は出なかった。野沢さんは黙っている私を見て、いつか笑うのをやめていた。不思議そうに、首を傾げている。 「ああ……あの、ですね」 「言いにくいことを言わなきゃ、と思ってるんですか?」 「……はい?」 そしてとうとう、よく気のつく笑顔の上手なその人は、私が何か言う前にそれを察してしまった……まぁ、見合い相手とのデートで言いにくいことを言うというのは、たいていそれしかないわけなのだけれど。間抜けづらをぶら下げて私は彼の顔を見やった。彼はそのまま、 「僕も、そんなに鈍いわけじゃないですから、わかりますよ。この話しはなかったことに、でしょう?」 私は何にも言えなかった。彼は苦笑しながら、いいんですよ、お見合いなんですから、と柔らかく言った。私は、はあ、すみません、と言って頭を下げ、お茶を飲み、とんとんとうまくいきそうな、そうでないような変な感覚に捕われながら、お菓子を食べた。何だか申し訳ないなあと思いながら、でも初めからことわるつもりの話だったしなぁと思いながら、ずるずると食べたり飲んだりし続けた後には、美味しいはずのお茶の味もお菓子の味も、あまり感じられなかった。野沢さんはその後にもうまく話題をつないで、この頃出張が多くて、実は漬物が好きなんでしょっちゅう買ってきてます、なんて話をしてくれた。お茶漬けにするとおいしいんですよ、と言った彼の顔は、好きなものの前で素直になったその顔で、私はさらに申し訳なくなった。でもこれも、世間では日常茶飯時なのだろう。お見合いをする人がいて、うまくいかない人がいて、うまくいく人がいて、片思いされたり、したり、それとは別に恋していたり。統計では、何分かに一回結婚があって、離婚があって、と言うけれど、みんなこんな変な、ひょっとすると重いいやーな感じで、その何分かに別れたりしているんだろうか。別に、嫌いでやめるわけじゃない。かと言って好きになったわけでもない。その気がないからことわった。とか言いながら多分、こういうのをひきずったりするんだろうなぁ、私はそういう人だから。そう思うとかなりゆううつだった。あーあ、ゆううつ。最近いいこと、少ないなぁ。 「じゃあ僕はこれで」 すっと、そう言って野沢さんは席を立った。手にはちゃんと伝票が握られていて、私はあわてて、それは払いますから、と言ったのだが、彼はいえいえ、とんでもない。わざわざ僕なんかにつきあってくれたお礼ですよと言って、さっさとレジに向かってしまった。私は一人取り残され、一緒に出るというわけにもいかず、その背中を無言で見送った。見送って、何とかきりはついたけれど、何か後味悪いなぁと、変にしみじみ思ってしまったのだった。帰る途中一人で立ち寄ったカフェで熱いダージリンを飲むと、それは苦いばかりで全然おいしくなくて、なんて損な性格なんだろうかと、また改めて思った。 新しい週が始まって、まず最初のアクシデントはゆかこさんからの電話だった。いいお話だったのに、ことわったんですって?と言う彼女は心底残念そうで、でも、じゃあ他の方にも会ってみない?という具合で、全くこりていない様子だった。私は、しばらくお見合いする気はないから、と、今度こそようやく自分でことわることができて、とりあえずその話はクリアになった。これでしばらく静かに暮らせるな、野沢さんのことはちょっと悪いことしたけど、と思っていろいろを仕切り直そうという頃、また事件は起こった。 ひまが少ーしできて、インターネットの活用法もまあまあ覚えて、デジカメの使い方もうまくなってホームページ「ちーほーつー」も、何とか運営というところにこぎつけた、その頃。 「この間ちょっと使わせてもらってたら、そっくりのページ見つけちゃった」 新しいお店を見つけて、その店のデータをまとめて、さぁ更新だ、とパソコンの前に座った私に言ったのは、妹のみやこだった。お風呂上がりにソーダ味のアイスバーを食べながら私の部屋をうろついていた彼女は、振り返った私に向かって言葉を続けた。 「おねぇページの作り方、手ぇ抜きすぎなんじゃない?」 「って……あんたに言われる筋合いないと思うけど?」 「でも、似たようなのがあるってことは、そういうことでしょ?知らないよ?著作権だ何だ、って言われても」 「だって……この作成用ツールの通りに作ったら……こうなっちゃったんだもん、仕方ないじゃない」 自分ではよくできていて、結構お気に入りだったレイアウトを悪し様に言われて、私はちょっとご機嫌斜めになってしまった。妹も私も、デザインを作るといったような才能は、はっきりいって無いに等しい。しかし世の中は便利なもので、そういう人でも簡単便利にできるツールとかキットが存在している。多分そのページ作った人も、同じツールで作ったんじゃないの?とはみやこの弁だった。 「どっちが先か後かはわかんないけど、もう少し手ぇいれなよ?手伝おうか?」 別に悪気があって言ってるんじゃないよ、と、みやこは真顔で言った。私は何も言い返さず、その場で、そうした方がいいのかな、いいんだろうな、と考え込んでしまったのだった。だがしかし、働くお嬢さん(一応OLだし)には、請ったデザインを作るヒマもないし、その前に一体どうしたらいいのかなんて想像もつかない。レイアウトを変える、とかしてみたら、とみやこは言い、 「たとえばー……バーチャルカフェ、とか作るの。どう?」 「どうって、そんなこと言われても、私にできるわけないでしょ?」 「そりゃ、おねぇには無理かもしれないけど、カヅ君だったらやれるんじゃない?」 みやこはそう言って、ナイスアイディア、と付け加えて笑っていた。確かにカヅユキに手を貸してもらえたら、この魔法の箱でもっとおもしろいことはたくさんできると思う。しかし、 「そう言えばカヅ君、こないだ来たっきり全然顔見せに来ないね、珍しい」 みやこの言う通り、最近カヅはうちに顔を出さなくなっていた。原因は何となくわかるのだが、私はあえてそこに言及はしなかった。 「まぁ、あてにできない人はおいとくにしても、もうちょっと芸のあるホームページにしないと。おねぇだってまねっこって言われるの、いやでしょ?」 そのみやこの一言には一理あって、私はその場で考えてしまった。確かに。人がない知恵絞って一生懸命、ツールにしたがってだけれども作ったものを、まねだパクリだと言われるのは忍びない。 「そうねぇ……もう少しいろいろ、手を加えてみますか」 そんなわけでその日から、私の「勉強」が始まったのだった。 「へぇ……それで美術館か……珍しいと思った」 いろいろに造詣の深いあやこと久々に出かけると、最近お声がかかんなかったけどどうしたの、と言われたので、私はざっと彼女にこれまでの事情を説明した。あやこだって電話くれなかったじゃない、と言うと、 「そこはそれ、あんたの「とっかえひっかえ」が終わるかと思って」 と冗談めかして言った後、実はこっちもちょっと忙しかったのよ、と付け加えた。二人で温泉に行ってからは、実に一カ月近く過ぎていたけれど、たった一カ月で実にいろいろあったなぁと感慨に耽っていると、 「でも結局当分、とっかえひっかえかぁ」 と、ややあきれ口調であやこは言った。私はちょっとふくれて、 「だから、そういう言い方やめてよ。別にそういうつもりでしてるんじゃないもの。それに、今は結婚する気なんて全然ないの。忙しくて」 「じゃ、やっぱり彼氏もいらない?」 「……そんなひまもないなぁ。はっきり言って」 そっくりなホームページ発見後から、みやこは私を応援してくれるようで、毎月購読している雑誌やら何やらをまず私に提供してくれた。おねぇはこういうの読んだりしないから、無いセンスがよけいに無いのよ、とかなんとか言われてぐさっと来たけれど、この際そういうことは気にしないことにした。レイアウト、カラーリング、フォント、などなどなどなど。なるべく気をつけて見るようになると、それはそれはいろいろな形やパターンがあって、今まで気がつかなかった私って一体何、と思ったりもした。考えてみればパソコンは、時々頼みもしないのにグレードアップしてくれる誰かがいて、いろいろな機能が満載だったし、使えば使うほどいろいろな発見があって、まさに魔法の箱と言った感じだった。お茶を飲みながらの作業が楽しくなってきた頃、私はそれにどっぷりはまっていた。平日も土日もパソコン三昧。作るだけでなくてよそを覗いたりして、見ず知らずの人にメールを送ってみたり(最初はドキドキものだったけれど、なれると楽しくてたまらなかった)送られてみたりして、インターネットを通じた不思議な知り合い達が徐々に増えていった。うわー、これは結構楽しい、いや、かなり楽しい。そんなこんなで見た感じ、部屋にこもって一人作業、というややネクラな遊びに、私はすっかりはまりこんでいたのだった。とは言え、メールもホームページもやっぱり、お茶とコーヒー三昧で、要するに私は、自分と同じような趣味を持ったたくさんの人に、こういった形でめぐり会えてうれしかった、プラス小可愛いものを造形する喜びを得た、と、そんな感じだった。おかげでいろんなことを覚えて、ホームページもすっかり生まれ変わっていた。 「でもねぇ、いやなこともあったのよ?例のそっくりなページ作った人から変なメールが来ちゃったりして」 「へーえ、それは大変だ」 「いわゆる迷惑メールも結構来たし、電話代もかなりかかるようになって、お母さんにしかられたりしたし」 かつてISDNの何たるかも知らなかった私は、最近それをADSLにしようと思い立って、またいろいろと勉強もし始めていた。ネットも定額に切り替えて……その料金を払うことになって、財布も痛くなった。でも、毎日がとても充実している。 「でもおかげで、ちょっと寝不足なのよねぇ」 「にしちゃあ、元気じゃない。楽しそうだし」 「えー、わかるぅ?」 いまだかつてない充実感で、私は満たされていた。笑いながら言うと、いい感じだよ、とあやこが言った。実際体はとても疲れていても、気分はいつも爽快だった。紅茶やコーヒーを飲みに出かけるくらいしか楽しみの無かった私は、それをネタにしてまた楽しみを見つけた、そんな感じだった。 「けどねぇ、何もかもうまくいってはないのよねぇ、やっぱり」 「そう?またお見合い?」 「ううん……そういうのじゃないけど」 そして、いつも元気で毎日楽しくてアドレナリンの分泌量が多くなったりすると、こんなことを言われたりもするのだ。 「『彼氏でもできたのか?』とかねー……みんなどうしてそれしか言わないのかしら」 「何だ、そういうネタか」 心配して損した、と言いたげな顔であやこが言った。けれど私にとっては、それは結構深刻な、というか不思議な問題だった。みんな、他に考えることってないのかしら。そう思うと本当に不思議だった。別に、恋愛や結婚を否定したりはしない。ゆかこさんが言うように、いつかはそうしなきゃいけない、のかもしれないとは思う。その時が来たら、だけど。 「どうしてみんなそうなんだろう。ほかに夢中になれるものってないのかな」 「それはさ、やっぱり人それぞれだからねぇ。あんたみたいに茶乱でインターネットが大好き、っていうのもいれば、そうじゃない人だってたくさんいるわけだし。私みたいに温泉大好きな人もいれば、お風呂事体が嫌いなヤツもいるし」 信じられない話だけど、とあやこは付け加えた。そう、彼女の言う通りに、世の中にはたくさんの人がいて、みんながみんな、何か好きなもの、一生懸命になれるものを持っているわけではないのだ。 「大体、あんただって学生の頃は、短大出たらテキトーに就職して、五年もしたら結婚すればいいやーって、言ってたじゃん?」 「え?そ……そうだっけ?」 そうよ、と言って意地悪くあやこは笑った。私は、そんな大昔のことはすっかり忘れていて、ちょっとだけばつが悪くなった。あやこはにやにや笑いながら、美術館内の喫茶店にしてはおいしい紅茶を一口飲み、更に言葉を綴った。 「世の中男と女しかいないから、そういう意見に行っちゃうってのは当たり前って言ったら当たり前なのよね。何にもすることがなくて一人でぽつーんとしてるより、恋してた方が楽しいし。結婚だなんだって言われるのは、年を取ってけば仕方ないことよ?誰だっていつまでも今まで通りに同じにってワケにはいかないんだから。あんたもあたしも年は取る。我々の親の世代だって年は取る。そのあと一人でぽつーんといるよりは、自分のこと大事にしてくれる誰かと一緒にいたほうが、うれしいじゃない?」 「まあ……年を取ったりしたら、ねぇ……」 「でしょ?ついでに言うと、この国はまだまだ独り者の女の子には、いろいろと冷たいのよねぇ。給料にしても、職にしても」 まぁあたしはフリーターだから、と、言ってあやこは軽く笑った。言われてみれば、もくそもない。その通りだ。同期入社の男の人にくらべたら、実際私だって給料は少ない。事務職と現場の違い、と言われたらそれまでだけれど、額で言ったらわずかではあるけれど、少ない。それは本当。 「結婚したら楽かどうかはわからないけど、とりあえず一人でいなくていいし、つつましくやってれば旦那の稼ぎで食べていけるかもしれないじゃない?それに、結婚退職もはやらないけど、所詮準学士でしょ?しかもあんたはOL。この後何年長持ちすると思う?今の職場で」 だから結婚の話だって出てくるし、それは仕方ないことでしょう、とあやこは言った。私は特に言い返す言葉もなく、でも、まだまだ考えられそうにないなあと何となく思った。 「我々は、恋愛以外に楽しめるものがあってラッキーって、そう考えたらどう?」 黙り込んだ私を見かねたのか、苦笑交じりにあやこは言った。顔を上げると、彼女は更に言葉を綴る。 「だってそうじゃない?みんなもきっと他に何かは持ってると思うけど……恋愛がダントツ一番じゃないってことは、失恋しても一番の痛みじゃないってことよ?他でとりあえずストレスも解消できるでしょ?これってラッキーじゃない?」 「ら……ラッキーって……そうだけど……」 「言われるのは仕方ないけど、いちいち気にしてるのはバカみたいじゃない?そう思わない?」 「言われてみれば……」 そう難しく考えなさんな、と、笑いながらあやこは言った。我々は我々の道をいけばいいのだ。最近生き生きしてるけど、彼氏でもできた?なんて聞かれたら、内緒です、とか答えておけばいいのだ、とも彼女は言った。邪魔になるものをみんな排除することはできなくても、自分から間口を狭くすることはない。私たちは私たちの望むようにすればいい。社会的に排除されないように気をつけて。そう言ったあやこは同い年なのに物知り顔で、ちょっとだけ大人に見えた。そして彼女の言葉は、それを実行しているのか、とても重みがあるように聞こえた。説得力があって、なるほど、と思わざるを得なかった。でも。 「ねぇ、あやこ」 「ん?何?」 「あやこは、温泉が好き、なのよね?」 「……そうよ?」 何を今更、とでも言いたげな顔であやこは問い返してきた。私は首を傾げて、 「何か……ただの温泉マニアの科白には聞こえなかったんだけど……何かしてる?他に」 温泉マニアって何よ、失礼ね、と言ってあやこは少し笑った。そして、笑いながら私に答えてくれた。 「今ねぇ、そば打ち習ってんの」 「……そば?」 それは突拍子もなく、初めて聞く事実だった。あやこは、何と言うかさまざまに造詣が深い。テレビから流れてくる情報から、民間医療の薬から、植物のことから、温泉のことから、クレイアニメのことから、本当にいろいろなことを知っている。雑学クイーン、そんな人だ。だから何が飛び出してきても不思議はないけれど、何が飛び出してきても、いつも私は驚いてしまうのだ。余りにもとっぴょうしがなくて。 「……どうしてまた、そばなんか?」 たまたまそば打ち体験をやってみたらはまったのだと、あやこはすんなり答えた。そして、 「でも、他にもいろいろたーっくさん、やってみたいことってあるのよねぇ、これが。何か一つだけ極めたい、というよりは」 困ったもんよねぇ、そう付け加えてあやこは笑った。だから就職しても、フリーターでも、一つの仕事が長続きしないのよねぇ、と言った彼女は、それでも生き生きしていて、とても楽しそうだった。私はあぜんとしたまま、たくさんのやりたいことのある彼女を見て、確かにこれは、恋に燃えている女の子に酷似した顔つきだな、と変なことをしみじみ感じていた。もしかしたら恋と言うのは、男と女だけのことではなくて、何かに夢中になっている、その全てを言うのかも知れない。だとしたら私たちは確実に、いつも恋していることになる。彼氏はいなくても、いつも何かを追いかけて、手に入れようとしている。 「あやこって……仕事続かなくて飽きっぽくてマニアックでちょっと困ったちゃんだけど」 「……悪かったな、困ったちゃんで」 ほめるつもりで出てきた言葉は全くそれにふさわしくなくて、笑っていたあやこが眉をしかめた。私はそれでも、妙に感動していて、ほめるつもりで言葉を続けた。 「かっこいい……大人の女だったんだねぇ」 「……あんた、それはほめてるの?けなしてるの?」 しみじみと言い切った私をにらんで、あやこは言った。にらまれていても、私はほえーっとした顔で、すごいなあと思いながら彼女をずっと見つめていた。本心からのほめ言葉なのにどうして怒っているんだろうと、ちょっとだけ考えたりしながら。 そんなあやことのデート(笑)から十日ほどたったある日だった。最近調子がよくて機嫌がよくてお勤めも結構円滑に来ていたところに、事件はまた起こった。会社で、事務所で、さぁ今日も一日がんばるぞ、と一人気合いを入れながら頼まれた書類をコピーしていたとき、それは突然やってきた。 「松川さん、松川さん!いるか?」 「はい……何でしょう?」 現場から主任が一人事務所に駆け込んできた。彼は私を見るなり、怒鳴るように言った。 「客先が荷物届いてないって言ってきてるぞ!昨日の納期分!」 「……はい?」 「伝票と運送屋調べろ!海外に行く製品だぞ、あれ!」 コピー機の前で私は硬直した。全身から血の気が退いて、そのまま貧血でも起こすかと、一瞬そんな気さえした。うちの会社はあまり大きくない製造業で、扱っているのは主に機械部品だった。取引先はこの業界の第一人者的存在で、国内シェアも二位とか三位にランクされる大手で、子会社や下請けが意見しようものなら、明日の命も伺い知れないような殿様企業でもあった。その客先に、海外に送る荷物が届いていない。血の気どころの騒ぎではなかった。その一言で事務所はパニックに陥った。社長も専務も工場長もバタバタと会社中をかけ巡り、五つしかない回線の電話が引っ切りなしに使われ、関係のない部署からは、電話が使えないからどうにかしてくれという苦情までもがやってきた。主任は青い顔をして電話に向かって頭を下げ続け、上層部の方々は予備の製品を掻き集めろとか今から準備していつできるかとか相談を始め……私はと言うと伝票をチェックし直し、運送会社に電話をかけ、発送担当者に確認をとり、会社中を必死で駆け回る羽目になった。客先の引き取り担当に電話をかけ、調べてもらい、その間にまた別の仕事を片付け、気がつくとその午前中は瞬く間に終わっていた。頼まれていたコピーもとれず、書類も作れず、本日分の伝票も真っ白で、午後からもまた戦争のような忙しさが続き、一息ついた頃、上の方から呼び出しを食らった。客先は、強い。その仕事が止まってしまうほどのミスをすると、何千万という賠償金を払わなければならないこともある。今回は、とりあえずそういう事体にまではならなかったが、我が社の稼動が止まる寸前のパニックに陥ったことは、否めない事実だった。原因は、発送の時点で時間指定をするはずだったものがされていなかった、という、単純な確認ミスだった。確か時間指定の特別便を使え、という指示があったはずだが、と上司に言われ、私は絶句するしかなかった。伝票を作ったのは私で、運送会社を手配したのも私で、それを頼まれたのも私だった。他の誰のミスでもない、私がやったことだ。 「まぁ、人間誰しもミスはするから、こういうこともあるだろうけれどね」 言われて、はい、すみません、以後気をつけます、と言う以外、私には何も言えなかった。すさまじい凡ミスで、情けなくて涙さえ出そうになった。気をつけなさい、と重ねて言われ、私は自分の持ち場に戻った。朝まであった機嫌の良さも、がんばろうという決意も、すっかりかき消えてなくなってしまっていた。あーあ、とんだバカをやらかしちゃった。サイテー。恥ずかしさと情けなさのあまり、会社を辞めちゃいたい気分だった。 「……いかんいかん、前向きに行かなきゃ。前向きに」 呼び出された会議室から事務所に戻るまでの間に、私はそうつぶやき、両手でぱしぱしと顔をたたいた。しっかりしなきゃ。こういうときには普段以上に。済んでしまったことはもう取り戻せないけれど、この先同じポカだけは絶対しないように、気をつけなくちゃ。でも、一度なくなってしまった元気はそう簡単に回復してくれず、体は変に重く、頭は異様に疲れていた。このまま、溶けてなくなっちゃいたいなぁ、そんなことを考えながらのろのろとした足取りで事務所に戻ると、時計は定時を過ぎていて、人気もそこからかなり消えていた。仕事は、まだ山のように残っていて、私は残業を余儀なくされた。事務長はそんな私を見て、無理はしないようにと声をかけてくれたけれど、手伝ってくれるわけでもなく、すぐに室内から姿を消した。一人孤独に私は、ようやく本日分の仕事に取りかかって、何とか終わった時一人で泣いていた。何もかもがいやで、わずらわしくて、どうして私はこんなところで、こんなことしているんだろうと何度も考えた。考えて、考えて、会社なんかやめてしまいたいと、そんな気分にさえなった。でも、そういうわけにもいかないのだ。少し前に事務員がすでに一人減っていて、会社側からの勧告ならば仕方もないけれど、もう一人減ってしまったらここは大変なことになる。みんなに迷惑はかけられない。それ以前に、収入がなくなって困るのは自分だ。仕事をやめるわけにはいかない。やめられない。だからまだ、ここに来て働かなくちゃ。出来るだけしくじらないように気をつけて。そう考えて、また私は少し泣いた。泣けてしまって、どうしようもつらくて困ってしまった。でも、どんなに哀しくてもつらくても、生きていかなくちゃいけない。生きている限りは、どんなに大変でも、夜の次には朝が来る。夜が終わったら明日が来るのだ。そう思って、私は抜けた力を振り絞って、とりあえず帰宅した。帰ってご飯とお風呂を済ませると、明日のためにたくさん眠ろうと、勢いのままに布団に潜り込んだ。そして布団の中でぐずぐずまだ泣きながら、やがて眠ってしまったのだった。 それからしばらく、私は「前向きにいかなきゃ」と思ったにもかかわらず、とんでもなく沈んでいた。些細なミスから起こった大騒ぎが思った以上にこたえていて、会社にいるのがとてもつらくて、毎日憂鬱な気分で事務机に向かっていた。そしてそろそろ忘れそうかな、と思われるときに限って誰かが、松川ちゃん、この間ポカやったんだって、とはやしたてて、浮き上がりそうになった私の気持ちを再びどん底につき落としたりした。味方は、いないわけではない。気にしちゃだめですよ、と言ってくれる後輩もいた。けれど、ああ、こういうときのぐさりと突き刺さる一言というのは、なんて重くて痛いものなのだろう。こんなにつらいことなんて、今まで生きてきてあったかしら、と思われるほど、私は疲れてショックで打ちひしがれて、次に何か言われたら泣くぞ、くらいの心地にまでなっていた。泣きたいけれど、そんなことしていたら仕事は滞る。人に迷惑がかかる。何よりそれでまた何やら言われたら、たまったものではない。大体、一度や二度の失敗でどうして他人にそんなふうに言われて、扱われなきゃいけないのだ。そう思うと心底悔しかった。人間の集団というものの中にいると、良い人にもたくさん会うけれど、嫌な人にも必ず出会ってしまう。それが全くの悪人だったなら簡単に糾弾もできるし排除もできるけれど、そうじゃないから世間はややこしい。そんなこんなで、私はとてもブルーな気分だった。心労で、時折胃が重くなったりした。帰宅するとぐったりしていて、お茶さえ飲めない、そんな感じだった。 「……わー、本当だ。本当に顔色悪い感じだ」 金曜の夜、帰宅するとカヅユキが家族と食卓を囲んでいた。お帰り、ひなちゃん、という言葉の後に発せられたその言葉に、私はむっとして、 「何よ、人の顔見るなり」 「今話してたんだよ、みやちゃんと。最近調子が悪そうだ、って」 今日はお遣いで来たんだ、と言ってカヅユキは笑った。みんなが囲んでいるテーブルを見やると、その上に立派なメロンが乗っているのが見えた。無言でカヅユキを見ると、彼は笑ったまま、早く着替えておいでよ、食べるでしょ、何なら部屋まで運ぼうか、と言った。私は何も言わずに家族団らんの脇を通り抜けて自分の部屋に入り、そのまま、メロンの切られたキッチンへ行こうとはしなかった。食べる気なんて起こらない。この週末が明けたら、会社やめちゃおうかな。ずっとそんなことばかりを考え続けて、しばらくすると部屋のドアが外からたたかれた。 「おねぇ、メロン食べないの?」 みやこの声に私は、食べたくないからあんたにあげる、もう寝るから静かにして、と言って、本当に布団にもぐりこんだ。 「おーい、ひなちゃーん、起きてるかーい」 それからどのくらい過ぎたかわからない。声に気がついて私は目を覚ました。ということは……少し眠っていたらしい。何のためによく見えないのかわからない目をこすりこすり、私はごそごそと布団からはい出した。 「おねぇ、入ってもいい?ちゃんと服着てる?」 カヅユキの声に続いて聞こえたのはみやこの声だった。ちょっと待って、と言いながら私は完全に布団から出て自分の身なりをチェックした。少し眠ったせいか、先程より気分はすっきりしていた。けれどそれはさっきよりすっきりしていただけで、全部が全部ぬぐえたわけではなかった。ボタンをきちんとはめ直して、くしゃくしゃの髪を手ぐしで整えて、それから、どうぞ、と私は部屋の外に声を投げた。 「お母さんが、これだけでも食べなさいって。ほら、メロン」 部屋に入ってきたみやこはそう言って、しかし自分ではそれを持ってはいなかった。喫茶店のウェイターよろしく、カヅユキがその手にメロンと麦茶の入ったトレイを持って、傍らに立っていた。私は、まだ少し眠くて、後で食べるからしまっておいて、と言ったのだけれど、 「とか何とか言って、明日の朝ごろまでほったらかしにして、それでみやこが食べちゃったって聞いたら怒るでしょ?」 みやこは聞いてくれず、カヅユキも、そうだそうだ、とわざとらしくその意見に賛同していた。 「ほら、いいから食べなって。ね?」 二人が口をそろえてそんなふうに言った。私はそれを受け取って、すごすごと部屋の中に戻る。くっついて後から入ってきた二人は不思議そうに私を観察して、それから、 「何かこの頃すっごくおかしいけど、どうかしたの?」 「そうだよ。どうかしたの?」 温くなりかかったメロンを食べていると、みやことカヅユキがそんなふうに問いかけてきた。私はため息をついて、 「どうかしたよ?それが?」 どうせ、お勤めしたことのないこいつらに、こんな苦労はわかんないわ、と思いながら言葉を返した。みやこはその言葉にむっとしたらしく、 「何よ、その言い方。みんな心配してんのよ?」 というので、 「あんたなんかにはわかんないことよ。聞いてもむだでしょ」 「そんなことないよ、ねえ?カヅ君」 「わかんないわよ、人に頭下げたことない人には」 私はあんまりいろいろ頭にきていて、そこに来てこの二人につつかれて、疲れておかしくなっていた。ストレスははち切れんばかりで、となると、口のきき方だってやっぱりおかしくて、誰かが思いやってくれている、なんてことはちっともわからなかった。更にいけないのは、みやこにはまだそこまで推し量る度量というかキャパシティというか、そういうものが備わっていなかったことだった。 「何よそれ!そういう言い方ってないんじゃないの?カヅ君だっておねぇのこと心配してんのよ?」 「だからほっといてって言ってるの!一人にしといてよ!」 「ほっとけないからかまってやってるんでしょ!」 「かまってやってる?やってるって何よ?私がいつあんたにかまってくれなんて頼んだ?そういうのを余計なおせっかいって言うんでしょ!」 「言ったわね!」 「ま、まあまあ!ちょっとちょっと」 そのまま行くとつかみあいの喧嘩になるだろう展開を止めようとしたのはカヅユキだった。にらみ合う私たちの間に本当に割って入って、困ったようにカヅユキは笑っていた。 「二人とも落ち着いて、ね?」 「だってカヅ君!今の言い方ってあり?」 「それはこっちの科白でしょ!」 「だからほら、落ち着いて、ね?」 しかし、そんなことで落ち着く私たちではなかった。みやこはみやこで、心配かけておいてその態度は何だ、大体おねぇは、と言い始め、私はことあるごとに、あんたなんかにはわからない、疲れているんだからほっといてくれ、をくり返し、しまいにはおたがいの欠点を重箱のすみをつつく勢いであげつらい始めた。 「大体おねぇは外面ばっかりいいから、うちでしか爆発できないのよ!」 「外も内も、すっぴんもメイク後もないあんたに言われたくないわよ!」 「何ですって!失礼ね!メイクぐらい毎日してるわよ!」 「そうだっけ?てっきりくまだけ隠してるんだと思ってた」 「ひどっ……ひどぉい!おねぇだってメイク落としたらしみだらけのくせに!」 そうして、しばらく罵詈雑言が続いた。 「言ったわね、この年増女!」 「とっ……年増?まだ青いようなのに言われたかないわよ!」 「売れ残り!まがり角!厚化粧!」 しかし、その辺りで私はいわゆるクリティカルヒットというのを与えられ、そのまま絶句してしまったのだった。傍ら、カヅユキは逃げたそうな心底困った顔で、仕方なさげに私たちのやりとりを見ていた。後から、申し訳なかったな、と思ったけれど、直中の私たちにはそんなことに気をまわしている余裕はなかった。女の戦いというものは、得てしてこんなものよね。 「はい、そこまで!」 声とともに私たちの顔の目の前にさっと手が振り下ろされた。視線をさえぎったその手の主を探して目を上げると、お茶とお茶受けを持ってきた母の姿がそこにあった。 「お……お母さん?」 「みっともないのが下にまで筒抜けよ?若い娘がそろって、はしたないと思わないの?」 その一言で、まるで条件反射のように(半分くらいはきっと条件反射で)私たちはだまりこんだ。母はため息をついて、困った顔で固まったカヅユキを見、 「カヅ君、ごめんね。こんなのが二人もいて。うるさかったでしょ」 「あ……いやぁ、なれてるから」 その言葉を聞いた母は、まぁそれもそうね、と短く言って部屋をさっさと出ていってしまった。私と妹はそんな母を見送り、運ばれてきたクッキーと新しいお茶を見つめ、一応、止めに来たんだろうなあと思いながら、ほぼ同時におたがいの顔を見合った。みやこは少し拍子抜けしたような驚いた顔で、多分私も同じような間抜けヅラで、どちらからともなく口を開いた。 「ご……ごめん」 「ううん、こっち、こそ……」 「……このクッキー、おいしそうだ、ねぇ」 「うん。た、食べようか?」 「そ……そうだね」 あは、あは、あはは、あはははは、と、微妙な笑い声を立てて私たちは同時にクッキーに手を伸ばし、ほぼ同時にそれを口に運ぶ。ここまで来ると、けんかをしていたことはすごく昔のことのようで、そしてとてもばかばかしいことになっていた。けれど変な気まずさだけが残っていて、間を持たせるためにへらへらと笑うしかなくなっていた。変な話だけど。かたわらで見ていただけのカヅユキば吹き出したのは、それからすぐのことだった。カヅユキはそのまま、その場で腹を抱えて笑い始める。何がおかしいのよ、と言ってみたけれど、滑稽なことは自分が一番よくわかっていた。カヅユキはげらげら笑った後、私たち二人を見てこう言った。 「昔っから、パターン全然変わらないよね、二人とも。そんなにお母さんが恐いの?」 「こ……恐いなんてもんじゃないわよ」 専門用語でトラウマ、というのだろうか。幼い頃けんかをしていた私たちが下された母の鉄槌は、その幼さにしてみれば死に近しい恐怖を感じさせるものだった。何をされたか?今となっては大したことではない、とだけ言っておこう。その頃の記憶が残っている私たちは、この歳になっても母には勝てない、というか、それを思い出して逆らえないのだった。まあ……ありがたいことに、特別ヒステリックでもないし、悪いことさえしなければ、ごく普通の人だったけれど。本当にパターンすぎて笑えるよ、と言ってカヅユキはげらげらとまたしばらく笑った。私たちはばつが悪くなって、もう一度おたがいの顔を見ながら、ごめん、こっちこそごめん、と言い合った。それから、先にみやこが、何か変なの、と言って笑い、私も、そうね、と言って笑い始めた。さっきまで怒っていた自分はもうどこにもいなくて、寝起きの時よりもずっと、私はすっきりしていた。もう一度私はみやこに、それからカヅユキにごめんなさいとありがとうを言った。そして、照れかくしに、 「おわびに特別おいしいロイヤルミルクティー入れてきましょう!」 そう言って立ち上がると、二人は顔を見合わせて笑った。 「おねぇって、本当にお茶ばっかり」 みやこが言った。カヅユキは笑いながら、 「でも、ひなちゃんはこうでなきゃね」 そんなふうに言った。本当にお茶ばっかり。思って、私も笑った。 |