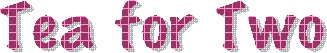|
|
―二人でお茶を―
第四話
|
「そう言えばカヅ、あんた最近顔出さなかったけど、何してたの?」 とびきりおいしいロイヤルミルクティーの後、私は思い出したようにそう彼に問いかけた。フィアンセ騒ぎの一件から、来にくかったせいもあるのだろうけれど、実際今日はかなり久々の来訪だった。みやこも、そうねぇ、どうしてたの、と、最後の一枚のクッキーを食べながら、彼に問いかける。カヅユキは困ったように笑って、 「いやぁ、別に、大した理由じゃないんだけどさ」 「だから、どうしてたのよ?」 ごまかそうとしているのは明白だったので、追い討ちをかけようと思ったのに、彼は。いいじゃんそんなこと、と言ってその話題について答えようとはしなかった。別に、何事もなければかまいはしないのだが、もしかしてその年でプチ家出でもしていたら、と、思わないでもなかった。妹も似たような心境なのだろう。うちにいるときは気にしないけど、よそでふらふらしてたら困るわよ、と、やや大げさに怒ったフリで言い、あはは、とカヅユキはそれを聞きながら軽く笑っていた。何事もなければ、いいにこしたことはない。いや、いいことがあるのならその方がいいに決まっている。私たちは、血縁はないけれどイトコで幼なじみで、なくしがたい友人でもあるのだから。 「結構人生順調にいってるよ?僕は」 「ふーん……あ、この前の女の子とは、どうなったの?」 やや生意気なことを言ったカヅユキに何気なく私は問いかけてみた。みやこは、何その、この前の女の子、って、と言いながらカヅユキを見、彼は、困った顔で笑って言った。 「……あれ以来、電話してない、です」 何々、どういうこと?と、みやこが首をつっこんできたので、私は細かく、自分の知りえる情報をその場で述べてあげた。これこれこういう理由で、私がフィアンセに仕立て上げられちゃったのよ、と。みやこはおどろき、それからちょっとだけ嫌悪の目をカヅユキに向けて、一言。 「サイテー」 「きついなぁ、みやちゃんは」 「だって、別れられないのなんて、カヅ君の度量が小さいって、ただそれだけの理由じゃないの?それを人の手借りてまでどうにかしようって、ふざけんじゃないわよ、って感じ。おねぇもおねぇだよ?人がいいにも程がありすぎ。断ればいいんだって、そんなの」 「……そうよねぇ」 被害者の私に対しても、みやこの意見は厳しかった。 「けどその女の子のほうも、ちょっと考えっていうか……足りてないわよね。相手が自分に気がないって、わかんないのかしら」 「さ……さぁ」 「にぶい女は恋愛の勝者にはなれないのに。ねぇ?おねぇ」 そんなことをそんなふうに言われても、私は何も言葉が見つからなかった。みやこはそのまま続ける。 「見てみなさいよ、おねぇを。一人でふらふらしてたらよりどりみどりよってたかってくるのに、好きになれそうなヤツとそうじゃないヤツの区別もつけられないのよ?もったいない」 「みやこ、私は別にそういう……」 「おねぇはだまって聞いてなさいよ」 はい、と私は短く答えて、それ以上は何も言わなかった。今日のみやこはいつも以上に話に熱が入っていて、途中で腰を折ろうものなら、見逃すことなくかみついてくるんだろうなと思える、そんな勢いだった。 「常に相手がどう出てくるか予測を立てていかなきゃ。株取り引きと同じで恋は駆け引きよ?押したら押されるだけでもだめだし、押し返すだけなのもだめ。たまには引いたり、引くフリをしたり、こっちから押したり引いたりしなきゃ。カヅ君なんか見た目からして女の扱い上手そうな顔なんだから、私は簡単に落ちないわよ、ってがんばったり唐突に懐に飛び込んだり、いろいろ手はあるはずよ?なのに、何?一方的に好き好きオーラ出して、フラれそうになって必死にしがみつくなんて、やり方が下手じゃない?そんなんだから盲目的に好きになっちゃって、土壇場で話がこじれたりするのよ」 しばらく、みやこの独壇場が続いた。私たちは顔を見合わせて、その、ありがたいんだかそうでないんだかわからない講義に、ただ耳を傾けていた。 「カヅ君もカヅ君よ?言いにくいことをばっさり言うのが、男の役目ってものでしょ?確かに、優しいのは一つの魅力よ。けど決断力が伴わない優しさなんてただの優柔不断じゃない?別れよう、とか、言ったら傷つくなあと思う時点でもうそれは男の罪よ?どうせ女の子は失恋した後に強くてきれいになっちゃうんだから、申し訳ないなんて下手な同情しなくたっていいのよ。それより、ああまだこの人私を好きなのね、なんて思わせたら、自分で好き好んで泥沼にしてるのといっしょなわけ。最後に来て別れようって言いづらいんだったら、最初から声かけなきゃいいんだから。最近の奴らはそういうところを全く考えてなくていけないわ。ついでに、女を見る目がないわよ」 「は……はあ、さようで……」 「それから、女のほうもよ。優しいってだけでくっついていくのは本当に何にも考えてない証拠だわ。男は優しいの、女は強いの。そういうものなの。ついでに、好きな人に優しくしないなんてどうかしてるわよ。優しくしてくれない人は、自分のこと好きでもなんでもないわけよ。優しくて当たり前なの。この人は優しいわ、ついでに顔も好きかも、って、それだけで彼氏を選ぶのはアホよアホ」 言って、みやこはそこでようやく一息ついた。しかし、一息ついてロイヤルミルクティーで軽く喉を潤すと、まだまだその講義は続いていきそうな勢いだった。 「他に何かとっつけるものがなきゃ、つきあってってたった何のメリットもないわ。一緒にいて楽しいのも当たり前。好きなんだから。後は好みの問題だから、私は何とも言わないけど。ま、理想としてはそんなところよね」 「り……理想?」 それにしては、何とも言いがたく現実的と言うか真に迫った言い分だったなぁと私は思った。みやこはそう、理想よ、と付け加え、 「なかなかそれにぴったり来る人は世の中にはいないわよ?最低条件をクリアしても、もう一つが足りない、とか。おもしろい人なんだけど、優しくない、とか」 「じゃあ……今の彼氏は?」 「ちょっと優しい方が足りないかもね」 とか言いつつ、高校生の頃から五年近くつき合っているのに、と、内情を知っている私は何となく思った。それはでも、そこまで来たらもう、足りるとか足りないとかじゃないんじゃないだろうか。 「じゃあ、みやちゃんは、その理想がやってきたらそっちに乗り換えるんだ?」 反撃のチャンス、とでも思ったのか。微かに身を乗り出してカヅユキが問いかける。みやこは笑いもせず、 「どうかしら。なにしろ愛があるから」 と、余りにもあっさり返した。私は何も言わないまま、宛の外れた答えにがっかりしているカヅユキを見ていた。何だよそれー、と言いながら、子供みたいにカヅユキはふくれていた。みやこは、この中で一番年下だと言うのに、妙に悟ったような顔をしてお茶を飲み、男と女なんて、そう簡単にくくれないわよ、と、いやに淡々と言った。見ながら、変なところだけこの子はお母さんに似たなぁと、私は複雑な気分だった。感心と言うか、恐れと言うか。それがないまぜになった状態でそう言うのは、ほめてもけなしてもいないと思って、私は口を出すのをやめた。 「とにかく、カヅ君は一人で決着つけなさいよ。今時は女の人のストーカーも珍しくないから、いっそのことそういう方面から責めていく、とか」 「みやちゃん……何か恐い」 リアルで過激な提案に、カヅユキは辟易しながらその感想を述べていた。私は無言で、ひたすらお茶だけを飲んでいた。 結局その夜は、何故か私もカヅユキと一緒にみやこに一晩中説教を食らわされ続けた。攻撃が一方に集中して隙ができた瞬間に眠ろうとすると、おねぇ、話しはまだ終わってないわよ、と捕まり、逆に集中砲火を浴びせられる、といった具合で、とまぁこんな具合よ、わかった?と言って終わりかけると、すでに東の空は白みかけていた。その間、私は何度もお茶を入れさせられ、眠くなったらカフェインとりなさい、と珍しくみやこにそんなことまで言われ続け……。 「みやちゃん、俺、帰らないと……」 「遠慮することないわよ。私たち親戚なんだもの。ねえ?おねぇ」 身内でも他人でも、こんなのはもう二度とごめん被るよ、私は胸の中でそう言って、表面では乾いた笑いで答えた。カヅは、わかった、はっきりふってくるから、もう十分わかりました、勘弁して、と、話を終わらせるために土下座までして言った。みやこはまだ不服だったらしいが、よろしい、じゃあ今度は決着が着いたその報告をしてもらいましょう、と言い放ち、条件反射のようにカヅユキは、ははーっ、と頭を下げたままで言ったりしたのだった。 「……とまぁ、こんなこともあったわけよ」 「へぇ、みやこちゃんが。ま、あんたがその類の説教たれるよりは、ずいぶん説得力があっていいんじゃないの?」 その翌日、最近どーお、とあやこからのいつもの電話があって、私は笑いを交えながら、会社でのことや、その後帰宅してからのみやことのけんかのこと、さらにカヅユキが説教されてそれに巻き込まれたことなどを話したりした。あやこはくすくす笑いながら、なんだかんだ言って人生エンジョイしてるのね、と少し不思議なことを言った。 「まぁね。けど、今まで通りで、何にも変わってないけど?」 「じゃあさー……ちょっと冒険、してみない?」 「冒険?」 首を傾げると、その様子が電話の向こうでわかったのか、あのね、と言ってあやこは話を切り出してきた。 「あんたに会いたいって人がいるのよ」 「私に?なんで?」 まあちょっと聞きなさいよ、と言ってあやこはその人のことを話し始めた。短大生の時入っていたサークルの先輩の知人という人で、インテリアコーディネーターをしている人がいて、その人が、副業でやっている仕事の助手を探している、とか何とか。 「インテリアコーディネーター?」 「今流行りのカフェなんかのコーディネートもしてる人で、あんたのこと話したら、ホームページ見たらしいのよ」 「へぇ……それで?」 でもインテリア屋さんの助手で、どうしてあのマニアックなホームページが関係あるのかしら、と私は考えた。あれは、ただひたすら私が好きなカフェやらお茶やらのことを、写真を交えながら好き勝手に星をつけたり、勝手に宣伝しているだけの、本当に遊びでやっていることだ。カフェのコーディネート、というあたりがちょっとだけかんではいるけれど……それ以外、何が? 「とりあえず、今度いつがヒマ?あ、できたら日曜の日中はさけてくれる?仕事があるから」 一人で首を傾げる私に、ややあわてたようにあやこが言った。私はしばし押し黙り、 「その人……男の人?」 「ううん……セレブのお姉様、ってところ。あ、男の紹介のほうが良かったとか?」 おどけて、あやこが問い返してくる。あんた見合い失敗したところだったもんね、と更に付け加えられて、私は一人露骨に眉をしかめた。 「……あんたまでお見合いの世話やくのかと思っただけよ」 「あたしが?なーんでとっかえひっかえの女に男の世話なんかしなきゃならないわけ?あんただったらぽやーっとどこかで紅茶でも飲んでたら、その辺から勝手に男がわいて出てくるでしょ?そんなむだなことしないわよ」 面倒な上に、とあやこは付け加えた。いつもの辛口な意見に何も言い返さないまま、私は彼女と次に会う約束を取り付け、じゃあね、と言って電話を切ろうとした。けれどその前に、何となく問いかけてみた。 「あやこ、そばはどう?」 「あー、あれ?」 聞き返して、すぐにあやこはうひゃひゃと笑った。世の中不景気で、通ってたそば打ち道場がつぶれちゃってさー、と、いつもと全く変わらない口調で、あっさりあやこは言った。だからしばらくは、花屋の仕事をきわめるつもり、と、彼女はその後続けて、 「なかなか、この世の中ってままならないものよね」 「そうね。なかなか上手くいかないのよね」 「けど、生きていくには何かしなきゃいけないし。難しいやね」 「でも、花屋の仕事を極めようって気分になれたでしょ?その分ラッキーじゃない?」 いつか彼女に聞いたような言葉を口に出して、私は思わず笑った。あやこは、お、上手いこと言うねぇ、と言ってやっぱり笑っていた。私たちはラッキーだ。好きなこと、熱中したいこと、できることがあって、生きていかなければならない長い時間の多くをそれに当てられる。退屈な時間が、その分だけ少なくてすむ。ただご飯を食べて眠って起きて働いて、という単純なサイクルの中に、ほんのちょっぴりのエッセンスを加えて、そのおいしさを味わいながら生きていける。それじゃ、今度の水曜の夕方あたりに、と私たちは約束して電話を切った。待ち合わせはどうしよう、と言うので、私が、いつもの駅に着いた頃携帯に電話してよ、とだけ言って返すと、 「また新しいところ?」 「まぁね。やや渋目の、落ち着いたいいところよ?」 「へーえ。じゃあ、楽しみに待ってますか」 そう言い合って私たちは電話を切った。それにしても、あやこは一体どんな人を連れてくるんだろうと、その後私は自分の携帯電話を眺めながら、ふと思った。 水曜は一応「ノー残業デー」という扱いになっている。うちの会社では、事務の担当者の残業と言うものは原則としてありえないもので、してもほとんどの場合手当が着かないと言うすばらしさ(?)だった。上の方いわく、事務処理くらい時間内にやれ、ということらしく、私としてもその辺についてはちょっとどころかかなりの不満だった。けれど、現場の方々に言わせるとデスクワークで稼いでいるだけでも腹が立つこともあるらしく、時折、いいよな、事務はよ、と無責任な愚痴までかまされることもあった。冗談を言ってもらっては困る。事務だって大変なのだ。私たちだって働いているのだ。そりゃあ、現場にくらべたら腕力仕事はないし、汗だくになって働くというスタイルも、ほとんどとらないけれど、それでもやっぱり、働いているのだ。しかも最初から、給料がやや安かったりするのだ(うちだけかもしれないけれど)そんなに言うんなら自分でやってくれ、と一体何度言いたかったことか。とまあ、そんなことはさておき。 水曜日はそんなわけで、誰に文句も言われずに定時で会社を離れられる、いい日だった。六時ごろにいつもの駅近く、と約束していた私は、その約束の時間よりも五分ほどその場所に着いて、たぶんここらにいれば見つけてくれるでしょうとたかを括りながら、流れていく人ごみを、少しだけ離れて見ていた。まだ一週間の終わりでもないのに、繁華街近くは人であふれていた。近くにオフィスがあるから、みんなきっとそちらから流れてくるのだろう。スーツ姿の、明らかに帰宅と注の会社員や、学生と思しき一団、おへそを出している女の子や、くたびれたTシャツの少年達。これから出勤と思しきお姉様方や、これからが就業時間のスーツのお兄さん達。世の中にはたくさんの人がいて、その人それぞれの生き方で生きている。何ちゃってマンウォッチを楽しみながら、私はしばらく一人でそこにいた。時計はそろそろ約束の六時近かったけれど、向こうも働いているのだから、多少の遅れは気にしないことにした。 「ひなこ、さんっ」 ためらいがちの男の人の声が私を呼んだのは、そんなこんなでひまつぶしをしていた、その時だった。聞いたことのある声は、振り返らなくても誰のものかはすぐわかったけれど、私はそちらへと向き直った。呼ばれた瞬間にびっくりしていたから、改めて驚き直したと言うことはなかったけれど、 「の……野沢さん……」 その人を見てから、びっくりした、と私は口に出して言った。すごい偶然ですね、と、いつかお見合いをしてお断りしたその人は、人の良さそうな顔でにっこりと笑った。スーツ姿でアタッシュを持った彼は、そのまま、誰かと待ち合わせですか、とまるでそれが流れのように問いかけてきた。私はええまあ、と言って、何となく視線を、また人混みに戻した。野沢さんも、どなたかと、と問いかけると、彼は笑ったまま、 「今、帰りなんです。会社、そこですから」 と言って、後方のビルを指し示した。言わずもがな、この人は中堅の広告代理店の、営業さんだった。彼はにこやかにそのまま、 「待ってるのは……彼氏とか?デートですか?」 「いっ……いいえ!友達です!友達!」 やや意地悪な態度で聞かれて、私はあわてて否定した。別にあわてることもなかったのに。野沢さんはくすくすと笑って、 「へぇ……食事でも?」 「ええまあ……そんなところです。ああ……短大の時からの友人で、女の子ですよ?」 聞かれもしないのに私は何故かそこまで答えていた。野沢さんは、何がおかしいのかずっと笑っていた。別に、この人に、そんなに友達を強調することもなのに、と、私は言ってから少し思った。いや、まぁ……ほら、お見合いの最中に二股かけてた、とか、思われるのも難だし。うん。それだけの理由……でももう終わったことなんだし、ここで会ったのもほんの偶然なのだし、別に言い訳じみたことをすることも、全然ないのだけれども。そんなことを一人で思っていると、かばんの中で携帯電話が鳴った。ほら来た。女の子からの電話よ、と、何故かまた胸の中で言って、私はそれを取ろうとして、相手の番号を見て眉をしかめた。かかってきたのは、けれど、あやこからではなかった。なんでこいつが、と思いながら出て、私はもしもしも言う前に、耳がきーんとするほどの音にその場で見舞われることとなった。 「あ、ひなちゃん?ちょっと頼みたいことがあるんだけど今どこ?」 誰言おう、電話の主はエセイトコ、カヅユキからだった。私は思わずはしたなく、ちっ、とか舌打ちして、今どこも何も、と言いかけたのだが、向こうは全く聞く耳を持ってはくれなかった。 「今みずきに捕まっちゃっててさ……迎えに来てくんない?ほら、この間お茶した辺り……」 「って……あんた、彼女とはすっぱり別れるって、そう言ったじゃない?」 みっともなくもエセイトコは、例の彼女とまだきちんと話をつけられないでいたらしかった。それで私に救援を頼みたい……全く、どうしてそういうことをするのかしら。私はあきれて、物も言えなかった。 「うん、そのつもりだったんだけどさぁ……やっぱ目の前で泣かれたりすると上手くいかなくて……」 男の言い訳はみっともない。女がしても、それはやっぱりみっともよくない。あーあ、とため息をついて、私はためらいも何もなく、電話を切った。どのみち、今日は助けに行きたくなったとしてもできないのだ。先約があるんだから。ざまぁみろ。自分で起こした不祥事くらい、自分で何とかしろ。そんな気分で携帯をたたむと、傍ら、野沢さんは小首を傾げてこう言った。 「どうか、されたんですか?」 「……あ、いえ、どうも」 額をひくひくさせた顔つきから一転、私は言葉とともにもう笑っていた。やや間があったことは否めないけれど。野沢さんは苦笑しながら、女の人はすごいですね、と、静かな口調で感心したように言った。 「僕の会社の女の子達もなんですけど……特に受付の人かな。いつも笑っていて……」 「いや……そ、そういうもの、ですか?」 でもそれって、外面がいいって暗に言われてるみたい、なんですけど。それにいつも笑っているというのは、褒められた事なのかしら。そんなことを思いながらも、私は彼に問い返してみた。くすくす、と、微かに笑い声を彼が漏らしたのは、その直後だった。 「僕は会社に入った頃、どうしても笑えなくて、上司に散々言われてましたから」 「わ……笑え、なくて?」 そういう彼は、何がおかしいのか屈託なさげに、くすくすとずっと笑っていた。私は、あれだけ見事な営業スマイルのできるこの人が、笑えなかったなんて、と思うととても意外だった。顔中で多分言っていたのだろう。言葉にしなくてもわかったらしく、意外ですか、と、彼は軽く言った。 「い……意外も、何も……ええまぁ……」 「でも営業ですから、笑顔が第一でしょう?愛想も良くなくちゃやっていけないし。何度やめようかって思いましたよ。けど我慢して努力したおかげで、主任なんて肩書きをもらって……まあでも主任なんて、班長みたいなもので大した役でもありませんけどね」 そう言ってまた彼は、くすくすと笑い声を立てた。だから時々、同期入社でやめていったヤツなんかと会うと、おまえは恐いよ、って言われますよ、と、彼は実に楽しそうに話した。 「最初は、必死に働いているんだからへらへらなんて笑えるか、って思ってたんです。いくら営業でもね。僕らの仕事は、半分くらい自由業だと思っていないと神経がまいるような事もよくあるから……真面目だったんですねぇ、あの頃は、自分でも意外に」 でも実は、入って三年もすると別の部署に移動もできるんですよ、と彼は言った。私がすかさず、じゃあどうしてずっと同じところにいるんですか、と訪ねると、彼はこう答えた。 「同期のほかの連中の中には、どうしても広告デザインがやりたくてうちに入った人間もいて、そういう人間の三分の一くらいはそこで挫折していったんです。うちの会社は入社三年は全員営業、と決まってましたから。けどその後希望の部署に移ってから会社から消えていった人間も、実は結構いるんですよ。僕は、特に夢も希望もなく会社に入って、とりあえず働こうと思っていて……なんと言うのかな。特別ここで生きていこう、こういうことしよう、とは考えていなかったんです。だから移動する先のことも、いっさい頭にはなかった。ついでに言うと、すごいものぐさですから」 「ものぐさ?」 「ええ。仕事を与えられていないと、何もしないと言うか……どういったらいいのかな。飽きっぽい上に、同じことをし続けると言うのが我慢できない性なんですよ」 軽く言って、軽く笑って、野沢さんは言葉を続けた。 「今している仕事も確かにパターンと言えばパターンなんですが、お客様が違ったり依頼が違ってくれば、すべて違ったやり方になってくる。口八丁手八丁、なんて言いますけど、八丁どころじゃ足りないくらいです」 「は……八丁、ですか?」 いまいち言っている意味がわからなかった。野沢さんは笑いながら、おかげで退屈しないですんでいる、という感じですよ、と、言いながら、くすくすといつかのように笑ってみせた。 「なんだかんだ言って、向いてるんですよ、この仕事。嫌いじゃない……と言うより、続いているって事は」 「そう……ですか」 「はい」 ではそれは、笑っていなければいけないというのは、頭を下げて時にはしかられなきゃいけないというのは、苦痛じゃないのかしら。胸の中だけで私は思った。思ったついでに、あることに気がついた。彼の笑い方は、確かに営業用のそれではあるけれども、嫌なところがない。にっこり、は、たしかに作ってあるのに、ぎこちなさが全く見えず、見事なきれいな営業スマイルなのだ。そして多分彼は疲れているであろうにもかかわらず、その笑顔を滅多に絶やさない。多分会社でも、取引先でも、商談中でも、こんなふうなのだろう。思うと、やや感動だった。私も、四六時中笑っているけれど、きっと四六時中はこんな顔をしていないことだろう。疲れてため息もつくし、いらいらして眉もしかめるし、内心バカヤローと言いながら必死で笑っていることもあるから、見られたものじゃないと思う。でもこの人の顔には、それが、そんな感情の色が、全く見えない。上手く隠されているのかもしれないし、もしかしたら裏がないのかもしれない。 携帯電話が再び鳴り初めて、私はそんなことを考えている最中だと言うのに、あわててそれを手にとった。今度こそかけてきたのはあやこで、私はすみません、と短くことわって電話に出た。ごめん遅くなって、今どこ、と問われて、何番出口のそばの、と答えると、その電話は向こうからすぐさま切られた。ぴ、と、こちらも通話ボタンをオフにすると、 「じゃあ僕はこれで失礼します……もう会ったりも、しないでしょうが」 野沢さんは最後に会釈をして、そのまま人混みの中に紛れていく。変な、出会いだった。見送って、私はそんなことを少し思った。それから少し待つと、やーごめんごめん、遅くなって、とあやこが現れた。時計は六時半近くになっていて、あやこは私の前で手を合わせて、 「ちょっとこっちの仕事がてこずっちゃって。あ、宮本さん、こいつがあのホームページの主です」 そう言って後ろを少し振り返った。そちらを見やると、私たちよりわずかに年上に見える、パンツスーツ姿の女性の姿があった。 そう言えばここは、野沢さんが連れてきてくれたところで、最後の話をした場所だったなあと、私はその店内を何気に眺めて思いを巡らせていた。あやこが連れてきた、年上のセレブのお姉様、もとい、私に会いたいと言った人は、ここはあのホームページにはのっていなかったわね、と、ハスキーな声で言い、メニューの作りや店内の内装を興味深げに眺めていた。 「じゃ、改めて。こちらが宮本さなえさん。あたしの先輩の知り合いで、うちの花屋のお得意さん」 それでこちらが、とあやこが言葉を続けるのを制して、私は先にその場で名乗った。 「松川ひなこです。どうも」 セレブのお姉様、宮本さんは初めまして、と言って手をさしのべた。驚きながらそれをとると、彼女はタイミングを見計らったように、言葉を紡いだ。 「ホームページ、おもしろく見せてもらってるわ。中傷メールなんかも来たんですって?」 ええまあ、と答えてあやこを見やる。へへ、と、あやこは笑って、何も言わないまま、いろいろアピールしておいたわよ、と顔だけで教えてくれた。私たちは、夕食にしてはちょっと物足りないようなメニューを見て、その中から各々好きなものを選んで頼み、何かいつにもまして渋い店ねぇ、とあやこが言ったのを聞いて、厳密には自力で探したところじゃないしなあと、私は何気に思った。 「松川さんは、喫茶店をめぐるのが好きなんですってね」 本日のお勧めコーヒーセットの抹茶ケーキを切り崩しながら、宮本さんはさらりと話を切り出し始めた。 「ええ……まぁ……」 それにしても、あやこはこの人と私を会わせて、一体どうしたいんだろう。思いながら私はくろもじで、目の前の、いわゆる常用まんじゅうを小さく刻んだ。彼女は、おいしいわね、この抹茶ケーキ、と言いながらそれを食べ、コーヒーを飲み、また店内を見回す。内装やインテリアに興味があるというのは明白だった。そういう仕事だと先に名乗っているし。店内は、全体的にジャパネスク風だった。和風と言うより、ちょっとだけヨーロッパテイストが混ざった感じの……何と言うべきかしら……あ、アールヌーボー?あの頃のパリ万博の展示室の一部、にしては渋目の……モダンジャパネスク?色調はモノトーンがメインで、時折アクセントに入っている赤色が、赤と言うよりも朱という具合の、黄色の混ざった強い色だった。手びねりの、こだわりの器も、渋目の色で統一されていた。 「いい趣味ね、このお店も。春海好みの器でも出てきそうだわ」 言って、宮本さんは少し笑った。は、春海好みって何、と、聞きたかったけれど……多分言わなくても、まったくわからない顔をしていたので彼女には伝わっていることだろう。コーヒーを飲み、ケーキを食べ、彼女はまた笑った。そして私をまっすぐ見て、言葉を紡いだ。 「ねぇ、松川さん。私のところで働いてみる気はない?」 「……はい?」 それは少し唐突で、私は、冒険ってこのことか、と思いながら、無言であやこの顔を見やった。うわー、お抹茶と和菓子だよ、と言いながら干菓子セットを食べていた私は、そんな私の顔を不思議そうに見返しただけだった。 宮本さんの話を簡単にすると、ざっとこんな感じだった。今までアシスタントをしていた人が結婚するのを気に仕事をやめる、と言うので、その欠員を埋める人材を探している。できたらパソコンに詳しくて、インテリアやテーブルウェアに興味のある、若い女の子がいい。フードショップのコーディネーターもしているので、そういうものに興味があればなお良い。で、それを聞いたあやこが、喫茶店をめぐって写真を撮ったりする趣味の友達がいるという話を彼女にして、ページのアドレスを彼女に教えたのだそうだ。で。 「今ここで決めてほしいとは言わないわ。あなたにだってあなたの事情があるでしょうし」 そう言って彼女は目の前に名刺を置き、伝票をもってすぐに席を立った。わーいラッキー、おごられちゃったぁ、と、となりでおどけてあやこが言うので、思わず私は平手で頭につっこみを入れてみた。ぱしん、と、いい音が響く。 「ってー……何すんのさ?」 「それはこっちの科白でしょ。何、今の」 「おごってもらって……」 「違う、これ!」 更にボケるあやこに向かって私が、置き去りにされたその名刺を突きつけた。あやこは笑いもせずふざけもせず、ただ淡々と答えた。 「いわゆるヘッドハンティングでしょ?」 「ヘッドハンディング?私を?インテリア屋さんが?」 「コーディネーターよ、インテリア屋、じゃなくて」 軽くあっさりと、あやこが言った。私は驚いて、何も言い返せない……というか、言葉が出てこなかった。 「だから、あんたのホームページを見て、ぴーんと来るものがあったんだって。よくわかんないけど、色や配置のセンスが気に入ったんでしょ?きっと」 「で……でも私、そういう勉強なんか、したことないし」 パニックになって、しどろもどろになって、でも何故か私はしゃべっていた。あやこはあきれの笑みを浮かべて、 「してたじゃないよ?パクリだ、っていうメールが来た後で。珍しく美術館とかデザイナーズブランドの店覗いて歩くようなことして」 「ああ……あれは……さ、参考になったらいいなーって、ちょっと思っただけで……」 しかし特別何かに反映されている、とは自分ではまったく思っていなかった。勉強と言うより、あれは流し見のような気もするし。あやこは、あんたってヤツは、と言いながら笑い、そしてそれから、言った。 「あんた、自分が好きで始めたことが認められたんだよ?うれしくないの?」 「う……うれしい、けど……」 じゃあとりあえずそれでいいじゃない、と言ってあやこは笑った。そして、これじゃご飯には足りないから、何か食べに行こうか、と付け加えた。私は呆然として、いまいちここで今何が起こったのかわからず、その名刺をぼんやりと眺めた。私が、ただ好きだというだけで、ちょっと布教してみようかな、というだけでやり始めた遊びを、そういう形で見ている人がいるなんて、思いもしなかった。ああ、ITって本当にすごい、たったあれだけのことで、ヘッドハンティング、なんて。 「ゆ……夢みたい」 「じゃ、本当かどうか確かめるために、ひっぱたいてあげようか?」 けらけら笑ってあやこが言った。私は名刺を手に取り、なんて上手い話なのだろうと自分で思い、とりあえず今日のところは、うれしい気分を味わってもいいかな、と思った。幸せがやってきたら素直に喜ぶ、それは自然のことだけれど、そうしてうきうきしっぱなしでいるほど、もう子供でもない。 「……あやこ」 となりの彼女を何気なく呼んだ。何、というので、私は言った。 「上手い話って……裏があるのよね?」 「さぁ、どうだろうねェ」 答えたあやこの顔は、少し意地悪に笑っていた。 それから、しばらくは足元がふわふわするような日々だった。そんな気分が、だめだと思いながら、どうしても抜けなかった。うれしくて、そのことばっかり考えてしまって、また会社でコーヒーとお茶を入れ間違えて注意されたけれども、そんなことは全然、痛くもかゆくもない感じだった。誰かが冗談まじりに、恋でもしてるの、と問いかけてきて、私は、もっといいものですぅ、と、浮かれまくって答えたりしていた。しかし私は、一介のOLなのだから……その仕事に支障が出ては、本当はいけないんだけどね。 「えー、でも、そっちの仕事のほうがOLよりおもしろそうじゃん」 この間はどうして助けてくれなかったんだよ、と言ってカヅユキがやってきたのは、それから二週間ほど後のことだった。パソコンを眺めて、どうしたものかな、と考えていたところに現れた彼に事情を聞かれて、私は気付くと素直に全てを話していた。ああ、まだ浮かれてるわ。しゃべってから私は自分でそう思った。それにしては元気がない態度で、カヅユキはそれを感じ取ったらしく、目をきょとんとさせていた。 「何……どしたの?ほめられてヘッドハンティングだろ?うれしくないの?」 「う……うれしいわよ?けど……」 何だか、複雑だった。そりゃあ、複雑にもなろうと言うものよ。この不況に、今のところ安定している今の職場を離れて、別の仕事に来ませんか、なんて言われたら。あなたの腕を買っているから来てほしい、みたいに言われたら。言いよどんで、私はそれ以上は言わなかった。カヅユキは首を傾げ、迷うことなんて別にないだろ、と、簡単に言った。 「やりたいことがあるんなら、やればいいじゃん」 「そう簡単に言わないでよ。あんたと私は違うのよ?」 「違うって、何がだよ?」 「そ……それは……」 いつまでもふらふらしている私立大学院生とOLじゃあ、立場も全然違うじゃない、と言いかけて私はやめた。そういう違いではない。もっと決定的な何か……いや、もっとあいまいなもの?とにかく、違うことは違うのよ、と、私はごまかすように言い、何それ、と言ってカヅユキは眉をしかめた。 「やりたいことがあって、できそうなんだろ?やればいいじゃん?恵まれてるよ?それ」 「ま……まぁ、そうなんだけど……」 厳密には、やりたいことなのかどうかはいまいちわからない。インテリアのことなんて全然わからないし、パソコンのことだって、カヅユキに教わりながらやっているわけだし。私はその場で眉間にしわを寄せた。眉をしかめて、その場でうなってしまった。 「……何、そんなに悩むことなの?まさか詐欺とか」 「ヘッドハントで詐欺って何よ?」 「……ありえないか。だまして得もしなさげだし」 何だかそれを考えただけで、私はぐったり疲れてしまった。カヅユキは私を見て、笑いもせずに言葉を紡いだ。 「興味はあるんだろ?なら、話をもっと聞くとか、実際どういうことしてるのか、見てくればいいじゃん。就職活動の最初って職場見学からでしょ?」 「しゅ……就職活動って……」 「まあ、ひなちゃんの場合はOLだから、学生の俺達とは違うだろうけど。けど考えてもみなよ?この不況に、人がほしいって言って、しかも名指しだよ?お買い得だと思うけどなぁ」 そういう問題かよ、と、突っ込みたかったが元気が無くてそれもできず、私は黙って、うなっていた。カヅユキはにぱ、と笑うと、 「それに、いやならいやって断ればいいだけの話だろ?このあいだの見合いみたいにさ」 あっさり言わないでよ、と、蚊の鳴くような声で私は答えた。ああ、思い出したくもない。あの時の気まずさと言ったら……一番私がいやなのは、お断りします、の、その瞬間のことだった。ノーと言えない日本人の典型どころか、最悪な形が私だと言っても多分過言ではない。確かに、この間はちゃんと、何とかお断りはできた。けれどその後、偶然にも鉢合わせしてしまって……何と言うか、ばつが悪いったらありゃしない。 「世の中の人間が、あんたみたいにみんなきっぱり物が言えるなんて、思わないでよね」 ややいやみったらしく私が言うと、カヅユキはあきれたように言葉を返してきた。 「それって何?自分ではっきりさせられないから、いらいらして人に当たってんの?」 「そ……そんなつもりじゃないけど……」 「ひなちゃんは、最初から保守的すぎなんだよ。もっと冒険してみればいいじゃないか。そうだろ?」 「そんな……無責任なこと言わないでよ。あんた私が困ったら、助けてくれるわけ?」 そう、その発言はいつでも、無責任だ。自分とはまったく関係が無いから、そんな格好つけたアドバイスなんかができるのだ。私は何だかそれが頭に来ていた。気に入らなくて、ムカムカした。 「助けるって……だってこれはひなちゃんの問題だろ?他人が手出しして、どうすんのさ」 「結局そうでしょ?何かあったら、自分で処理しなきゃいけないんでしょ?人事だと思って、言いたいこと言わないでよ。自分がその立場だったら、あんただってそう思うでしょ?」 いやまあ、そうだけど、と言って、カヅユキは口ごもった。私はため息ばかりを吐き出して、またパソコンと向かい合った。もごもご、としばらく小声でカヅユキは何か言っていたけれど、やがて彼の珍しい説教は再開された。 「ひなちゃんは、今まで恐いことしたことないだろ?まともに彼氏だって作ってないし、学校だって、推薦でしか入ってないし」 けれど私には、聞く気がほとんどなかった。 「……だから何よ」 「そういう風だから、ものもはっきり断れない、曖昧な感じになっちゃうんだろ?就職先だって家から近いってだけで決めてただろ?やりたいこととか、何かなかったのかよ?」 「……なかったわよ。土日が休みで、実家から通える近いところとしか、考えてなかったし」 「それで、ゆかこさんにお見合い勧められたら、なあなあでお見合いはするし?」 返す言葉は、なかった。カヅユキはやったとばかりに少し笑ったらしい。微かに呼吸の音が聞こえて、私はもっとむっとした。 「だ……だけどねぇ!私は私なりに考えがあってやってんのよ?あんたに言われたくないわ!」 「そりゃそうだろうよ。でも、あんまり考えてはないだろ?」 ううっ、言われてみればその通りよ、と、私はつきささる言葉の痛さに、胸の中だけでそう言った。そのまま、うろたえて動かない私を見たのか、背後でカヅユキが言葉を紡いだ。 「話だけでも聞いて、現場でも見て……それから考えてみたら?ひなちゃんの問題なんだから、他の誰も決められないことだし」 こくんと、私とはうなずいていた。カヅユキの言葉は理に叶っている。確かに今までの私は、人に勧められるまま、強い態度で断り切れずに、するずる何かをし続けるという傾向があった。とっかえひっかえと言われていることについてだってそうだと思う。愛想よく笑っていて、愛想がよすぎて誤解されて、なあなあでつきあい初めて、結局実りも何もないままに彼らは離れていった。今の職場でも、そうだ。とりあえず今のところ大きな事件は何事もなくすんでいるけれど、この先こんなふうでは、やっかいごとだって起こってくるだろう。こういうのは、そうじゃない私になるためのチャンスなのかもしれない。今までこんなに曖昧で、不満があったわけじゃない。でも、回りが言うように、私はもう少し冒険したりして、変わるべきなのかもしれない。そう思うと、今まで曇天のようだった心の中が、少しだけすっと晴れたような気がした。そうよ、いやなら断ればいいんだから、前向きにいろいろ考えなくちゃ、若いんだから、いろんなことにチャレンジしなくちゃ。そう思うと、気分はまたすっと軽くなって、逆に、何をぐずぐず考えていたのかと、それがばかばかしくさえ思えてきた。 「よし……いっちょやってみるか」 独言のようにつぶやくと、そうそう、そんな感じだよ、と傍らでカヅユキが言った。私は振り返り、彼の笑顔を見て、釣られるように笑った。 |