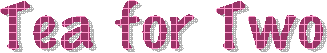|
|
―二人でお茶を―
第一話
|
同期の女の子が解雇されて、私の隣の席から消えた。同期とは言え年は二つ上の、普通よりちょっと虚弱だった彼女は、別段ぬきんでて悪いことをしたわけでもなければ、特別できる人でもなく、運悪くそういうお鉢が回ってきてしまった、そんな感じだった。リストラ。私たちはそういうものの対象として日々その会社に通い、勤め、奉公し(ちょっと違うかな)お給料をもらっている。ただ運が悪いと会社の延命のために、まるでガン細胞のように切り取られて、ぽいと捨てられてしまうのだ。そういう人がぽつぽつと現われ初めて二年、私は運良くここで生きのびていた。でも、いつ切り取られて捨てられてしまうかわからないのは、そうして消えた彼女と同じ。多分私が切られなかったのは、彼女より二つだけでも年下で、彼女よりも体が丈夫だったからだろう。でもこれも、運かも知れない。 「松川さん、まーつかーわさん!」 「あ、はい」 中小企業の事務員、格好をつけて言うと中堅の(そんな格好あるのかしら)OL。それが私、松川ひなこのパーソナリティとか、言うものだった。事務員、小さな会社だからいろいろと雑務をするのが私の仕事。世話役さんと言った方がいいくらい、その仕事内容は事務の範疇からかけ離れている。 「この書類、送っといて。それから……」 「こっちの伝票ですね。わかりました。午後からでいいですか?」 短大卒、家は近所。特別、何もないって言ったら何もない、あと二年もしたらきられてしまうかもしれない、もしかしたらもっと早く解雇されるかも知れないOL。それが私だ。現場から上がってきたいろいろを裁きながら、客先に送る書類を確認しながら、愛想よく笑っている。おかげでここまで五年間、大したアクシデントも起こさずやってこられた。特筆すべきは今現在、特定の彼氏という人がいないこと、くらいか? 「ついでに、今度の金曜だけど……」 「あ、そうだ忘れてた!自販機の業者さんが来るんだっけ。じゃっ」 作業服の先輩の言葉を遮るようにわざとらしく言って、私は彼とのおしゃべりを終えて逃げるように席を立った。彼氏いない歴……歴ってほどじゃないけど、三カ月。製造業の我が社には男性社員のほうが多く、その中では出会いに渇望している青年男子も、ままいたりする。とりあえず、今は彼氏はいいや。背中で舌出して、てな具合で私は胸の中でつぶやいた。普段の愛想のいい私なら、愛想よく金曜の夜のお誘いに返事もしようものなのだけれど。あ、一つ訂正。彼氏はいらない。今、大好きなものがあるから。 「彼氏いらない?うそぉ」 「うそぉって、そういう言い方しないでよ」 「だってあんた……とっかえひっかえだったくせに?」 「そういう人聞きの悪いことも言わないでくれる?」 窓の大きくとられたカフェのその窓際の席が、私と友人、梶川あやことの待ち合わせの定番だった。最近この手の喫茶店がそこいらじゅうにぼこぼこ増えまくっている。いいことだ。でもこの店は細かいツッコミをするとただの喫茶店ではない。夜になるとお酒が出るから、一応カフェバーかな。「ラ・ムーファ」という名のその店を見付けたのは今から半年ほど前だ。いわゆる盛り場の、ちょっと外れのビルの四階にあるその店は、窓からの眺めがいいことで最近有名になってしまい、静かな感じが好きな私としてはちょっと不満もあったけれど、ここでの待ち合わせはいろいろと都合がよかった。近くには大好きな輸入食材店があり、少し歩けば大きな書店があり、駅近く、とくればちょっとどころの便利さ加減ではない。あやこはテーブルの上の大きなパフェを長いスプーンで掘るようにして食べながら、私を見てその眉をしかめていた。 「何よ、その目は」 「だって……途切れたことないヤツが、珍しいなーとか思って」 「だから、そういういやらしい言い方やめてくれない?とっかえひっかえでもなきゃ、途切れたことがないわけでもないんだから」 「いーやっ、途切れてないしとっかえひっかえだね。この七年間、あんたがフリーだった事のほうが絶対少ないよ?」 「それは、そうかもしれないけど」 「男はあんたのそのかわいらしい外見に、いつでもころーっと騙されんだから。ったく……誰かに呪われてたりしないでしょうねぇ?」 「何よそれ」 あやことは短大の頃からのつきあいだから、そろそろ七年もつるんでいることになる。その頃からこういうちょっと口の悪い、がはがは笑う、さばさばっとした、それでもって世話を焼くのが好きそうな、そういう性格だった。ついでに知的好奇心が旺盛で、両親がまだリタイアしそうにないのをいいことに、好き勝手して暮らしているらしい。今仕事は、と訪ねると、花屋のバイト、と、にこりともしないで答えた。一応自分で食ってるよ、とは言うものの、この不況にフリーターと言うのは、友人としてはちょっと心配だ。 「このあいだテレビでやってたよ?現代の拝み屋さん特集」 「へーえ、今の面白いネタはそれか」 いたずらっぽく笑う彼女を少しにらみつけてやる。あやこはえへへ、とわざとらしく笑いながら、 「拝んでもらう時はついていってもいーい?」 「……このミーハー娘」 「やぁだ、純粋な好奇心じゃないのよぅ。それに、日本人ってこーゆー民族よぉ?」 「あそう」 冷たく言い放ち、私はアイスティーのストローに口をつけた。でも彩子の言っていることは、誇張はあっても、あまり嘘かなかった。特別そういう自覚はないけれど、いや十人並みだなぁと思ってはいるけれど、どうしてか知らないけれど男の人に受けが良いらしく、短大性の頃から彼氏に事欠いた事はなかった。別にいらないんだけど、愛想が良くて適当に笑っていると、いつのまにかそういう人になっていたりした。あやこいわく「そのとろそうな顔は癒し系なのよ、きっと。で、癒されるわけよ」だとか。人をセラピー用のぬいぐるみかなんかと同じに評して、彼女はけらけらと笑った。まぁ実際、そう言われれば自分でも納得できなくもないけど。そして、ちゃんと断らないからずるずる一緒にいると彼氏になっちゃうんだよ、と言うのも彼女の弁だった。でも、オトシゴロですもん。やっぱりちょっとくらいはもてたいじゃない?これって私だけ?違うわよね?さて、そんな具合に複雑な心境の私のことはさておき、あやこは、うわークレープが出てきたー、とか何とか言いながらこの店のウリの一つでもある特大パフェを食べて笑っていた。私は、どうしてそんなに大きな甘いものを一人で食べられるかな、と思いつつ、一応出てきた私のための長いスプーンを眺めた。役目がないそれはテーブルの上で、大人しく横になっていた。 「でも前の彼氏かっこよかったのに。どうして別れちゃったの?」 「男は顔じゃないでしょうが。それに特別好きでもなかったし……彼氏って言うより、アレよね。言うなればみんな遊び友達だもん」 あーあ、とため息混じりに私は言った。あやこは食べるのも笑うのもやめて、そう言った私を見つめた。何事だろうと視線を返すと、「遊び友達?全部?」 「そうよ?」 「じゃああれだけとっかえひっかえで、スキになった人っていないわけ?」 「うんまあ」 あっさり、私は返した。あやこは絶句し、手にしていた長いスプーンをいったんテーブルの上に置いて、それから、こほんと一つ咳払いした。 「何?」 「いやさ、ひなこ。じゃあ今まで愛もなくつきあってたわけ?」 「愛もなくって何?」 変に臭いことを言われて、私は思わず吹き出してしまった。あやこは黙って私を見て、何かしら答えでも待っているふうだった。笑いながら、 「そりゃあ、嫌いな人、はいなかったよ?遊び相手だから」 「遊び相手って、どういう?」 「どうって……ねぇ……」 侍らせていたわけでもなく、足にしていたわけでもなく、私と彼らの遊びと言ったら、暇潰しと映画と時々テーマパークで、夏場はプールだったりした。ご飯も、遊ぶうちに入るのかな。 「じゃあえっちとか、してないわけ?」 ちょっとだけこそこそ、と、でもいつも通りにずばっと、あやこは言った。私は眉をしかめて、この女は、と思いながら、 「あんたねぇ……」 「そこのトコロは結構重要じゃない?どうなの?それは遊びには入って……」 「ないわよ」 ずばり、私は返した。冗談じゃない、遊び友達と誰がそんなことするか。かーっ、とか言いながら、私は興味津々で変に目をぎらぎらさせているあやこを見やった。そして、その続きを言葉にして並べてみた。 「じゃあ聞くけど、あんた会社の同僚とか、近所の幼なじみとか、のべつまくなしにそーゆーことしたい?できる?」 「いやー……それは、できないけど……」 「高校生の時、クラスで仲のいい男の子としてた?」 「ひ、ひなこちゃーん……何か恐い……」 微かに後退りして、ひきつった笑みであやこが言った。わかったからそれ以上言うな、と顔中で言っていた。私はふぅと溜め息をつき、少しだけ乾いた喉を潤すためにアイスティーを一口飲んだ。 「……じゃあ聞くけど……も、もしかして」 「もしかして、何?」 「……そーゆー要求されたから、別れてた、訳?今まで全部」 もう食べないのか、スプーンをテーブルに置いたまま、どうしてか握りこぶしなんかを作ってあやこが問い掛けてきた。私はちらりと彼女を見やって、 「ま、中にはね」 どうだ参ったか、と言いたい心地で、その問いに答えた。 「はっきり言っちゃうと、いまいち「レンアイ」って言うの?そういうのがわからないのよねぇ」 ぶっちゃけた話、私はそういう人だった。彼氏というような人達は何人かいた。何だか私にはわからない理屈でやってきては消え、やってきては消え、一対一じゃなくて平気だと言った人達は、辛うじてメル友とかいうヤツで生き残っている。異性の友人です、と言うか、何と言うか。半年一回実物に会うか会わないかでも友と呼べるのは、そういうジェネレーションだからだろう。中には結婚している人もいる。そういう人とはその相手とも、お友達だと私は認識している……男女の友情は成立しない?そんなことないわよ。共通の話題があってフィーリングが合ってげらげら笑えれば、それでもう友達じゃないの?私の持論だけど。 「結婚願望とかは?」 「今はないなぁ……特別には」 「ラ・ムーファ」を後にして、私たちはウィンドウショッピングに繰り出した。町は若人と、春先の陽光とで賑々しく、スプリングフェスタ、で更ににぎわっている。 「でも別に、仕事に生きる、とも思えないしねー、今の職場じゃ」 町を歩きながら、私は笑ってそう言った。ほぼ手ぶらの私とは好対照に、やや荷物の多めのあやこは、ちょっとだけひーひー言いながら、私を追いかけるように歩いていた。 「そんなことよりさ、この先にまた新しいお店、見付けちゃったぁ。コーヒーの専門店でねー……」 「コーヒー?また飲むのかよ?」 呆れ顔であやこが言う。私はえへへ、と笑って、その店に向かって右腕を出し、人差指を立ててみた。 「いーじゃないの、これが私の道楽ですもの」 「まぁ……そうなんだけど」 「あんたの好きそうな手作りケーキなんかもあるわよ?」 にんまり笑って振り返ると、あやこは多大なる溜め息をついていた。私は拍子抜けして、疲れた彼女を見やって言った。 「……何?ケーキ好きでしょ?」 「一日にそう何個も食べないって……さすがに」 「あそう。じゃお茶でも飲んでればぁ?さー、いこいこっ」 その答えは、あんまりうれしそうではなかったけれど、私の方はと言えばもうほくほくで、足取りもぴょんぴょんと飛び跳ねそうなくらいに軽かった。多分いわゆる彼氏よりも好きなもの、コーヒーも紅茶もだけれど、それは今はやりでぼんぼん増えまくっている喫茶店を巡ること。私はこれが大好きで、楽しくて楽しくて楽しくて、本当にこればっかりなのだった。男の人なんかよりそれはよっぽど私の心をくすぐった。 「あー、A県民にうまれてよかったー、うふふふふ」 「そ……そこまで言うほど好きか、サ店が……」 背後で、慣れているはずなのにあやこが、今更そんな風につぶやいた。 友人達いわく、私の喫茶店熱は、異常だと言う。口を揃えて。私は、どうしてか昔からそのスペースが好きだった。子供の時から好きだった。高校二年から短大卒業間近までしていたアルバイトも殆どが喫茶店で、個人店の方がちょっと好きだったけれどチェーンのお店で制服を着たりもしていた。何だかあるところに行くととってもマニア受けの制服の喫茶店もあるそうだけれど、それはさすがにちょっといやなカンジだった。大きな窓、沢山のグリーン、時々インベーダーゲーム、リバーサイド、夏はぱきっと冷房で、気の利くお店だと空気清浄器があったりして、街のオアシスのような気分になれて、家では食べられないケーキやアイスクリームが一年中常備していて、自分ではうまく出せないおいしいコーヒーが出てきて、ちょっとした異世界のようなところだ。 「いや、そういうのは幼年期に終わるね」 「夢がないなぁ、あやこは」 「あいにく、そういうドリーマーじゃないだけだよ」 二軒目の喫茶店、正しくカフェ「しゅがーれす」の、やっぱり窓際の席についた私たちは、本日のおすすめコーヒーを頼んで、もう甘いものはいらない、と言ったあやこはアイスを、私はホットでそれらが出てくるのをその場で待ちながら、呆れたり呆れられたりしながら、そんな話に興じていた。ブラウン系で統一された店内の内装や、テーブルに置かれたミニグリーンを見ていると心が和む。昨今のカフェブームは、私にとっては「ビバ!」と叫びたくなるほどうれしいものだった。アジアン、フレンチ、オキナワン、アメリカン、イタリアン、ブリティッシュジャパネスクなどなどの、それぞれの喫茶店にはマスターの趣味で集められた雑貨があったり、突然変わったランチメニューがあったりと、そこはワンダーランドさなからだ。街はそのワンダーであふれて万華鏡のようで、その時の気分で色んな世界を楽しめる。 「そーゆー人はリ□ルワールドにでも行きなさい」 「ダメだよ、お茶もコーヒーもおいしくないもん。お手軽じゃないし近くで買い物できないし」 私の反論に、あやこは言葉もないようだった。人に言わせるとやや特異らしい私の趣味を、手を取り合ってわかってくれる人というのは少ない。せいぜいが「便利だね」という誉め言葉が出ればいいところだ。待ち合わせとかデートとか、そういうので使える、という程度。私としては、この小さな空間に感じられる宇宙と言うか世界と言うか、和みの空間だったりかえって刺激を受けたりするところだったりの、こんな面白い愛らしい魅力的なものはないと思っているのだけれども。 「まぁでも、あんたのすすめる店は確かにスウィーツも充実してるし、お茶もコーヒーもおいしいから、いいけど」 あやこと出かける時は大抵お茶をする。平均で2,7軒。食事というのは少ない。と言うより、ディナーをしたことはほぼない。お茶っ腹でご飯なんか食べられない、というのが彼女の言い分でもある。私も確かにお茶やらコーヒーやらでお腹いっぱいで、ご飯を食べたいと思うことは希なのだが。 「そう言えば、一緒にいると飯もろくに食えない、って言ってどこかに行っちゃった人がいたなぁ」 出てきたコーヒーをすすりながら、私はそんなことを何気に口にした。あやこは呆れ切ったらしく、変な顔で笑いながら、そこまで行ったか、と小さく言った。 「限定の紅茶買いに行った時に、俺より紅茶がいいのか、って泣いたのもいたっけ」 「そんなこともあったのか……」 「あれ?話してなかったっけ?」 初耳だよ、とあやこが言った。私は首を傾げて、どうしてそんなに疲れているんだろうと、何だか苦しげな形相の彼女を見て思った。 「あんたが「茶乱」てのは知ってたけど……ここまで来ると」 「来ると……何よ?」 「その男どもが哀れだよ」 ため息とともにあやこが言った。私は笑って、 「えー、でも男の子だってほしいものがあったら並んで買ったりするでしょ?ゲームのソフトとか」 「……そういうふうに言うか、あんたは」 「え?何かおかしい?あやこだって限定のシュークリーム、並んで買ってたじゃない?」 「いやまぁ……そうだけどさぁ……」 あやこの言葉はそこで途切れた。どうやら私とは見解が明らかに違うようだ。けれど私はそれを無視して、最近ハマっている楽しいことの話に話題を移行してみた。 「そういえば、この間エセイトコがパソコンのグレードアップしてくれてねー」 「エセイトコ、って……ああ、カヅユキくんだっけ?」 「うん、それ」 あやこが顔を上げた。私はえへへ、と笑いながら、 「新しい画像用ソフト入れてくれて、ほくほくなんだぁ」 「へぇ……パソコン。そういえばデジカメ、買ったって言ってたっけ?」 どうやらこの話題は、快く聞いてくれるらしい。良かった、と思いながら私は言った。 「でね、ホームページ作ってんの、今」 「へーえ……いいねぇ、詳しい人が近くにいると。じゃ、写真いっぱいとってたりするんだ?」 「うん。名付けて「ちーほーつー」ていうの。楽しいよ♡」 「……ちー?」 何だそれは、という具合に、あやこが眉をしかめる。私は笑いながら、 「喫茶店とかレストラン巡りのホームページなの」 と言うと、あやこは絶句した。あれ、何か変なこと言ったかな、と思っていると、彼女は言った。 「あんた、筋金入りの「喫茶バカ」だ」 「うん……最初カヅが「喫茶バカ一代」って名前にしろって言ってたんだけど……なんでわかったの?」 がくーん、という具合に、あやこの肩が落ちた。あれ、何か変なこと言ったかな、と思いながら、私はそんな彼女の様子を見ていた。 エセイトコ、天宮カヅユキは、一つ年下の学生、正確に言うと大学院生だ。私立の工業大学に通っていて、だって親が行ってもいいよって言ったし、とかいう理由で進学した、なかなかふざけた男だ。電子工学とかいうジャンルが専門で、キットでパソコンを作ってしまう、あやこいわく「ヤヤタクヤロー」である。どういう意味か?「ややオタク」……言いえて妙、と言うべきだろうか。イトコという関係柄昔から彼をよく知っているけれど、どちらかと言うとアウトドアが好きそうではない感じの、優男である。ハウスな人、と言うとまた違う意味になるので、ヤヤタク、でいいらしい。ちなみにあやこは「職場以外の用事でパソコンがいじれるヤツはオタク」と言っているので……それも偏見だとは思うんだけど。エセイトコ、と言うのは彼の自称だ。中学生くらいの時にそう言っていて、以来誰かに彼を紹介するときの枕詞になっている。エセ、と言うのは、要するに血が全くつながっていない、ということなのだが、どのみち親戚づきあいと言うものは、血のつながりと言うよりは親子兄弟というしがらみで成立しているものなので、殆ど関係がないから、よそのイトコ同志という人達とそんなに差はないと思われる。だから、言ってみれば近所の幼なじみよりもちょっとディープにつきあいがある友人、というくらいのものだろうか。 「よ、ひなちゃん。パソコン元気?」 あやことのウィンドウショッピングを終えて家に戻ると、何故かその姿があった。血がつながっていないだけあってカヅユキと私は全く似ていない。ちょっと卑怯なくらいに整った顔をぶら下げたぼんぼんくさい童顔男が笑っているのを見て、 「何カヅ、あんたまた来たの?今日は何の用?」 「ご挨拶だなぁ、また今日は。ってオレも近くに来たからちょっと寄っただけだけど」 てへへ、と軽くカヅユキは笑った。つい最近も、近くに来たから、と言ってちゃっかり上がり込んで夕飯を食べて帰っていったけれど、彼はそういうヤツだった。何故か、我が家に顔を出したがる。家はとなり同志の町内で、自転車でだって行き来ができるところにあると言うのに、自宅でご飯を食べたくないらしい。変なヤツだ。 「パソコンの調子どう?あのソフトちょっと容量食うから、今までのマシンで使いにくくない?」 人懐こい顔でカヅが言う。キッチンの冷蔵庫から水出ししてあるアイスティーのボトルを取り出し、私は自分と彼の分をそれぞれグラスに注いだ。何これ、また砂糖入ってない紅茶なの、とかぬかすので、ウーロン茶にはお砂糖入れないでしょ、と思わず言い返し、それからお茶を一口飲んで、私はパソコンに対する質問に答えた。 「今のところは不自由ないわよ。でも、色々できて面白いわね」 「でしょ。おしむらくはモニターとプリンタのバランスがさぁ……」 彼は、根っからそういうことが好きらしい。嫌いだったらわざわざ大学に入ってまでそんなことも勉強していないだろうけれど。グラスを片手にべらべらと、彼のパソコンのうんちく話が始まる。私はお茶を飲みながら、何気にその話に耳を傾けた。彼は一応、私の母方の伯父の息子になる。一応、というのがエセイトコの所以だ。私の伯父は生後半年足らずのカヅをつれた彼のお母さんと結婚して、彼の父親になった。だから血はつながっていなくても二人は親子で、私たちはイトコ、ということになる。彼も中学生になるまでその事実を知らず、当然私もそんなことは微塵も知らなかった。本当の父親という人の消息は知れない、といつか言っていたが、中学生の男の子にその事実はかなりショッキングだったらしく、以来長い長い反抗期が、いまだに続いていた。彼は伯父と、仲が悪い、と言っている。本当の親子じゃないしね、というのが口癖だったこともあった。とか言いながら、二人は変なところが似ていて、第三者としては笑えるものがあるのだが。 「それで、どのくらいできてるの?ホームページ」 「まだまだ全然。そういえば今日友達と買いものに行ってたんだけど、あんたと同じこと言ってたわよ?」 「同じこと?何?」 「「紅茶バカ」とかって。バカはいいんだけど、どうせ言うなら喫茶バカ……違うな、カフェバカ?」 あれ、と首を傾げていると、けらけらとカヅは笑った。ひなちゃんらしいや、と言うので、だったらなんで笑うかな、と思いながら、私はごくごくとグラスのお茶を飲んだ。 「そういえば、さっきゆかこさん来てたよ。聞いた?」 「ゆかこさん?ううん。また珍しい人が来たわねぇ」 ゆかこさん、と言うのは、私の母方の伯母だ。母は彼女の、ずいぶん年下の妹だと言うのにお姉さんという呼称を使ったことがないそうで(逆に年が離れすぎていて呼べなかったのかも知れないが)どうしてか私たちまでそんな具合に呼ぶくせになっていた。本人はもうおばあちゃまなのだけれど、おばさんと呼ばれないことはうれしいらしい。ちなみにゆかこさんのお子さん、私たちのイトコにあたる人達は私の母と年が近いためか、やっぱり叔母さんと呼ばずに、まゆこさん、と呼んでいたりする。そして母もそれを気に入っている。 「お正月以来じゃないかな……おかーさん、ゆかこさん来てたの?」 キッチンと続きのリビングでテレビを見ながら書きものをしているらしい母に声をかけると、母はテーブルのほうを向いたまま、 「あんたが帰ってくる前に帰ったわよ。ひなこ、ちょっといい?」 呼ばれて、私はそちらに歩み寄った。テーブルの上にはお煎餅があって、ついでに手を伸ばすと、そのそばに白くて大きな封筒があるのが見えた。 「何?これ」 「ゆかこさんが今日持ってきたの。お見合い写真」 はーあ、と、母が溜め息をついた。このくせさえなければ、いい人なんだけどねぇ、とぼやいた母は、ほとほと困った疲れた顔をしていた。にやにやと、背後ではカヅユキが笑っている振り返って改めて見なくてもよくわかった。 「ひゅーひゅー、すげー、ひなちゃん大人だねっ」 よく意味のわからない科白で冷やかされ、私は、何だそれは、と眉をしかめた。 ゆかこさんは今年五人目のお孫さんが生まれた、とってもかわいらしいおばあちゃまだ。その年齢にしては、と言うと変だけれどあかぬけていて、趣味はパンづくりで、その趣味が高じてパン作り教室の先生にもなってしまった。母より十七才も年上で、還暦はちょっぴり過ぎているけれどエネルギッシュで、おしゃれなんかも大好きで、なのに時代錯誤だった。結婚とか、そういうことに関しては。 「二十五にもなってふらふらしてるのはどうかしらねえ」 そう言って置いていかれた封筒は、五枚。気に入った方にだけお会いすればいいのよ、とか何とか言い残していったそうだ。でも御自身は大恋愛の末の結婚だったのだという。だったらそういうものの良さを知っているんじゃなかろうかと思われるのだけれども、彼女にしてみると私の今の年齢が、どうやら気に入らないようだ。ちなみにゆかこさんは二十歳で結婚している。私は彼女にとってはその点で、規格外扱いらしい。 「うわー、すごい。おねぇ、この人アタマ薄いよー」 五つ年下の妹が、私よりも先にその写真を取り出して、広げて見始めていた。夜十時近くになってもまだいるカヅユキは、何が楽しいのか一緒になって笑いながらそれらを見ている。 「ゆかこさんも、相当の趣味だなぁ、こりゃあ」 「何のんきに言ってるの、あんた達もそのうち同じ目に合うわよ?」 人事だと思ってすっかり楽しんでいる二人を見ながら言うと、妹、みやこはけろっとした顔で、 「アタシ彼氏いるもん、おねぇみたくとっかえひっかえじゃないし」 「とっかえひっかえじゃないわよ!アレはみんな友達なの!」 「はたから見てたら女王様だよ、ねぇ?カヅくん」 「うーん、オレ実際そいつら見たことないからなぁ……」 あはは、と、軽くカヅユキが笑って言った。母はその傍らでお茶を飲みながら、 「一人くらいこういうときのためにキープしておくんだったわねぇ、ひなこ」 ……どうしてこうも人事と言うか……自分の娘がとっかえひっかえとか言われて、どうして平気なんだか。まあ、そう言ってるのも自分の娘なんだけど。胸の中で全く承服できないまま、私はいつものようにがぶがぶとお茶を飲んだ。母は、そんな私をちらりと見て、 「どうする?お母さん、ゆかこさんに断るって言ってあげようか?」 「前もそうしたけど、こりてないじゃない。自分でする」 ゆかこさんには、前科があった。具合よくその時は友達に頼んで婚約者のフリをしてもらい、事無きを得たのだが(何故かそれが原因で彼は去っていった)後日それがばれてしまい、今回のごとき始末となったわけなのだった。 「でも、結婚する気がない、なんて言ってもねぇ……あきらめないわよ、ゆかこさんは」 「まー……そういう人だけど……」 とっても、いい人なんだけど、普段は。世話好きで……でもここまで来るとお節介って言うんだよね、こういうのは。私はため息をつき、リビングのテーブルの上に散らばった写真を見やり、さてどうするかな、と考えた。結婚?とりあえず今はそういう希望はない。レンアイとかいうものもよくわかっていないわけだし、それを飛び越えてする見合いというのは、ちょっと問題があるように思えるし。でも、多分このまま未来永劫やっていけるということもないだろう。長女だし、両親ともにまだまだ元気で現役だから今は心配ないけれど、いずれは隠居になるわけなのだし、そうしたら誰かが傍にいなきゃ、とは思うし。いらない心配だとは言われたけれど。 「試しにしてみたら?」 えへ、と、その言葉の後にみやこが笑った。隣で、やけに派手に賛同したのはカヅユキだった。ぽん、と手を打ったりしながら、 「おお!それ、いいかも」 「あんたたちねぇ……」 「だっておねぇ、今彼氏いないでしょ?だったら別に見合いくらいいいじゃない。あってみるだけ。ねぇ?」 「そうそう、社会勉強だと思って。ねぇ?」 いい考えだ、とでも言わんばかりに、都とカヅユキは顔を見合わせて笑っていた。人事だと思って、こいつらは、と思いながら私は何も言わなかった。言わなくても、大きな荒々しいため息と、がくりとたれた首とで、どういう心境なのかを誰もが見て取れるはずだ。 「そうと決まったらおねぇちゃん、気合い入れて写真見なさいよ!」 「誰も決めてないでしょ」 「そんなこと言わずに。出会いのチャンスは活用しないと、ねぇ?」 「ねぇ、じゃないでしょ」 交互に写真を勧める二人に、私はそれ以上何も言い返せなかった。確かに、そういう見方や言い方もできるけど、興味ないっていったらないのよね、まだ。 「ねえねえ、この人は?年近いし、商社マンだし」 「こっちは?ハゲてるけどいいスーツ着てるぞ?」 しかしそんな私をお構いなしに、何故かその二人はその見合いに対してとっても乗り気だった。自称「クールビューティー」の母は時にそこまでクールでいいかと言いたいほどのクールさ加減で、私を見てもう一度訪ねた。 「どうする?お母さん、断ってあげようか」 「……自分でする」 そして私は、面倒くさいなぁと思いながら、次の朝飲むための水出し紅茶を作り始めたのだった。人の身の振り方でやいのやいの言っている妹とイトコは、無視することにしたのだった。 ゆかこさんは、電話すると、あらひなちゃん元気?と、いつもの調子で言った。今日行ったんだけれど、お買い物してたんですってね。どこへ行ってたの?と会話は始まり、あらそう、お友達と、と来た辺りで、私はその話を切り出した。しかし。 「……お母さん、そろそろ夏の着物?」 受話器をおいて傍らの母に訪ねると、まだそれは早いわね、と言って彼女はため息をついた。 「まだ夏のでなくても大丈夫よ……どうせだから振袖でも着る?」 「振袖?うん、着よう、どうせだから……」 この期を逃せば次に着られるのは、きっと正月だろう。そんなことはさておき、ゆかこさんにとってはとんとん拍子に、そして私にとっては崖を転がり落ちるようなペースで、その話しはまとまってしまったのだった。申し訳ないんだけれど、私そういう気ないから、とか、おずおずと切り出したりしたから招いた結果なのは、わかりすぎるほどわかっていた。 「そういう話はびしっとことわらなきゃ。いくら本人が言っても効き目なんかないわよ」 申し訳ないけれど、なんて言うべきではなかったらしい。そんなことを後で言われても、しょうがないったらしょうがないことだったけれど。愛想が良くていい娘さんをやっていると、こういう困ったこともたまには起こる。それは、誰にでもいい顔をしようとしているからまねく、自業自得というヤツだった。どうせことわるんだからいいじゃないの、と母はしれっとした顔で言い、さらにに、でもだからってとっかえひっかえはねぇ、と小さくこぼした。 「だから、そういうのじゃないってば」 「あんた愛想だけは昔からいいから。誰に似たんだか」 「そ……そういうお母さんだって、愛想、悪……」 言い返そうにも、言い返す言葉はない。母は、自称に「ビューティー」がついてはいるが、自他ともに認めるクールであるのは間違いなかった。いや、自分で「ビューティー」をつける辺りは、実のところは全然クールじゃないのかもしれない。母は、私だったらもっとずばっとことわれるわよ、としれっとした顔で言い、 「成人式で着た晴れ着でいい?それとも、お母さんのお古の方、着る?」 「……お母さんの方」 やっぱりしれっと言われて、私は何も言い返せなかった。着物を着るのは、実は好きだ。短大生だった頃に和装の講座があってひまつぶしにとっていたから、いわゆる訪問着なら自力で着られる。さすがに振袖を一人で着ることはちょっとできなかった。あれは何と言うか、コツがいるのだ。人に着せることなら……ああでも、どうだろう。そんなわけで結局私はゆかこさんのすすめをことわり切ることができず、彼女が持ち込んだ写真の中から一人を選んで、後日その人と会うという約束をさせられてしまったのだった。スナップでいいから一枚写真を用意してね、とは、その電話を切る直前の、ゆかこさんの言葉だった。 月曜日からの平日は、気分がどんよりしているのは最初の一日だけで、後はちょっとだけ怒濤のように時間が過ぎていくものだ。会社の事務所の席が一つ空いて、その分忙しいのが回ってくるかしらと思っていたらそういうわけでもなく、ひとまず平和にその一週間は始まった。仕事は、確かにちょっとだけ増えた。けれど六人でやっていた仕事が五人に振り分けられたと言うだけで、自分としてはその負担は、あまり大きくはなかった。電話をとる回数が増えて、掃除をする範囲が増えて、面倒を見る伝票が増えて……けれどそんなには変わらない。残業することもあったけれどせいぜい一、二時間程度だったし、まぁこんなもんよね、と思う反面、一人減っても仕事がこれだけしか増えないとは、やっぱり不景気なのかな、とも思ったりした。松川さんは平気そうですね、と、後輩の女の子の一人がいつかこぼしていたけれど、確かにその通り、私は結構平気だった。引き継ぎにちょっとだけ不備があったりして、面倒なこともないではなかったけれど。これが全く違う部署に移されて、全然違う仕事を沢山やらされた日には、私だってきっとこぼすだろう。急変したわけじゃないんだしさ、と何気に後輩に言うと、彼女はちょっと不服そうな顔をして、それ以上は何も言わなかった。私は、その人にあんまり好かれていないらしい。でもそれも、苦にするほどではない。紅茶の葉っぱを量り損なって、ちょっときつい味になったくらいの、そんな不快。そのうち気にもしなくなる。舌の根も渇かないうちに、とか言うように(これはちょっと違うかもしれない) あーあ、お見合いかぁ、と、平和だとか安寧だとか言っている割に、些細なアクシデントを気にしないふりをしているくせに、私はそれについてやっぱり悩んでいた。やっぱり?当然?悩む?考える?うーん……気にしていた、かな。悩むというほど悩むことでもないし、考えないでいられないほどの大問題でもないけれど、でも一歩間違えば一生問題なわけだから、それに対していろいろ考えるのは当たり前?とにかく、うっとうしいくらいに私はそれを考えていた。思うと落ち着かない。考えたくはないけれど、考えざるを得ないような感覚だ。気にしていても仕方ないけれど、人間と言うのは「気にするな」と言われた些細なことほど気にしたりするものなのだ。言われるから余計に?それもアリだと思う。そのうち私たち事務員を率いている総務の長から、何かあったのか、と何気に問われたりしたけれど、いえちょっと、としか答えなかった。壁に耳あり障子に目あり。噂と言うのは自分がぽろっと言ってしまわなければ、大して立たないし広がらないものだ。多分。口が固いと言うほどではないけれど、軽いと言うこともない。厳守しろと言われれば話さないが、そこに言及されなければよっぽどのことでない限りは聞かれれば答える。そういう人が言っているんだから……信頼性、ないか。とりあえず今の問題は、お見合いだった。聞きつけたらみんながよってたかっておいしいネタだと言わんばかりに群がってくるだろう。極力黙っていよう。でも考えるのはやめなかった。そのうちめざとく誰かが、ため息なんかを着いているところを目撃したりして、何かあったの、なんて聞いてくるに違いない。そうは思えども、だ。 「松川さん、コーヒー二つ……松川さん?」 給湯室で来客用の湯飲みを漂白していると、外から声がかかった。お客様らしい。顔を覗かせた営業兼工場長が(そのくらいの小規模な会社だ、ここは)ため息を吐きながらシンクを眺めている私を見て、小首を傾げた。我に返って、 「あ……はい、コーヒーですねっ。えーと……いくつ……」 「二つ。どうしたの?ため息ついて。珍しい」 工場長は我が家の父より五歳ほど若い、けれど両親と似たような世代の人だ。子供のような私が多大な(肺活量の都合で)ため息をついていたのを、どうやら目撃したらしい。小首を傾げていぶかしげにこちらを見ていた。私は、 「ちょっと……お疲れ気味なんですよぅ。仕事増えちゃって。あ、すぐ持っていきますねー」 とまぁ、いつものように調子よく返してお客様用のコーヒーカップをいそいそと支度し始めた。工場長はちょっとの間そんな私を見ていたが、すぐに取って返してその場を去る。あー、イカンイカン。仕事に集中せねば。お茶汲みも、事務員にとっては立派なお仕事だ。大体、このくらいしか能がないということは、自分ででも自覚しているわけだし。私は仕切り直し、気合いを入れ直した。そしてとりあえずお茶に全力投球して、帰宅したら自分のためにちょっと特別なダージリンでも入れちゃおうかな、と、まだ昼前の時計を見ながら思ったりしたのだった。しかし。 「松川さん、僕コーヒーって言わなかったっけ?」 「あ、あれ?」 商談直後、工場長は困ったように私を見て笑っていた。応接室と言われる、一応区切られたブースの机の上には、緑の粉の残った湯飲みが二つのっかっていた。具合でも悪いのか?と問われて、私はもう笑ってごまかすしかなかった。 「あは、あは……あははははは……はぁ」 何だかお見合いをすると言う余波は、思っているより大きいらしかった。 その日はそれから大したアクシデントは、ないと言えばなく、あると言えばあった。伝票用のプリンタが紙詰まりを起こして発行が遅れたり、郵便局へのお遣いに行ったはいいけれど、発送するはずの封筒を忘れたとか……悪いことというのは続くものだ。果ては電話応対に追われ、日変わり持ち回りでする食堂の掃除が時間内にできず、手当のつかない残業を余儀なくされ……エトセトラ。 「厄日?」 「三隣亡?」 「金神遊行日?」 普段より少し遅く帰宅すると、順に妹、父、母が言った。後二つの意味がいまいちわからなかったけれど、こういう日をさすんだろうな、と無言で私は察した。 「お茶汲みくらいしか能がない人が、そのお茶汲みでミスするっていうのは痛かったわねぇ」 「おかーさん……それひどい……」 一人遅い夕食をとっていると、配膳係の母は淡々と傍らで言った。笑っているのは妹、みやこだ。 「でも大したミスじゃないじゃない。今日中にちゃんと片付けられたんでしょ?仕事も」 「まぁ……ねぇ」 逆に、慰められるとへこむものだなあと思いながら(笑われているからかも知れないけれど)曖昧に私は答えた。母はお茶を入れながら、 「ま、そんな日もあるわよ。人生楽あれば苦あり、って」 彼の有名なボレロの詩の一節を読むように母が言った。笑っているのは、やはり妹だ。 「そうそう、気にしない気にしない。おねぇの顔だったらたまの失敗もかわいく見えちゃっていいかもよ?」 「って……そういう問題?」 これは、慰められているのだろうか。実はなかなかきっつい攻撃かもしれないなあと思いながら、私はもぐもぐとご飯を食べた。すっかり疲れていて、おいしい紅茶を入れて飲もうという気分にはなれなかった。こういうときは、せめて甘いものでも食べるに限る、かなぁ。ごちそうさまをしてから、何かないかとキッチンを探し始めた私に、父が一言言った。 「まだ食べるのか、太るぞ」 ……その一言で私は食後のおやつをあきらめた。ひどいことを言う父親だ、と内心思ったのは、言うまでもなかった。 |