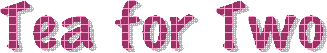|
|
―二人でお茶を―
第二話
|
「お見合い?あんたが?」 その夜、あやこから電話がかかってきた。彼女は電話が好きで、大した用もないのに週に一度ほど「元気?」と言ってかけてくる。こちらからも結構かけたりするけれど。まあまあ元気かもね、と言って何となく呼吸すると、受話器の向こうではそれが結構響いたらしい。ため息なんかついてどうかしたの?と言うので、多分原因はこれだろうなと口に出すと、彼女は素直に驚いていた。 「あんた男に飢えてないじゃない。なのに見合い?ちょっと贅沢すぎない?」 「だから、そういうふうに言わないでくれる?大体、今はフリーなんだから」 それに、今の世の中たかが彼氏がいるくらいなら、女の子はお見合いくらい平気でする。そのくらい贅沢に、いわゆる「マイベターハーフ」というのを探すことは、常識と言うか……悪いことではない。そう言って返すとあやこは軽く笑い、それもそうだ、と簡単に答えた。そして、でもまた、一体どういう風の吹き回しよ、と問いかけてくるので、私は素直に答えた。 「母方の伯母さんが、どうしてもって言うから……つき合いで」 「どうせあんたのことだから、強く言われて仕方なしに、でしょ?」 電話の向こうであやこが笑っている顔が簡単に想像できた。図星もくそもその通りよ、と言い返すと、やっぱり、とあやこは言った。 「まぁでも、適齢期だしね。そういう話が来たところで、何にもおかしかないわよね」 「そういう……まぁそうだけど」 「いいじゃない、社会勉強だと思って行ってくれば。あーでも、あんた気に入られやすいからなぁ」 けけけ、と小さく、しかし意地悪くあやこが笑った。人事だと思って、おもしろがって。私はひたすらため息をついて、やや痛い感じの頭に何気に手をやった。 「でもさぁ、結婚話にまで発展する前に、何とか切り上げなさいよ?なあなあで一生決められたら、しゃれにもならないよ?」 「当たり前よっ」 思わず、叫ぶように言った。けらけらと、まだあやこは笑っていた。そこまで私だって愛想良くないし、お人好しじゃない。遊び友達は、確かにほいほいできるけど(これも変って言ったら変よね、確かに)一生一緒かもしれない相手をそうもほいほい選べるわけがない。あーあ、気が滅入るなぁ。あやこにも話すんじゃなかった、と思っていると、あやこが不意に口調を変えた。 「そう言えば、今まであんたの好みって、聞いたことないんだけど」 「何よ、急に」 首を傾げて問い返すと、電話の向こうのあやこが、やや神妙な声で問いかけてきた。 「どういう人がタイプ?てゆーか……理想?」 「ど……どうって……ねぇ……」 言われて、考えてみて、思いつかない……こともないが、これと言って特別な要求というのも、なかった。私は少し考えて、 「そうねぇ……一緒にお茶してくれる人、かな」 「何それ。結局そこかよ?」 私の答えに、あやこが笑った。むむ、と私はその場で少し考えてみる。好みのタイプは、と聞かれて、例えば外見のことなら、普通の女の子だったら適当につらつらと理想も出てくるだろうけれど、私はこれといって面食いでもなく、どちらかというと「味のある」顔が好きだったりして(あやこいわく「飽きてるんだよ、あんたは」だって。ふん。どーせとっかえひっかえですよっ)でもかと言って、特別個性的な人というのも、ちょっとついていけない気がするし、理想は……おいしい水ならぬおいしい紅茶もしくはコーヒーのような人で……って、自分でもどんなのがいいのかよくわからないのだけれど。むむむ、と、もう少し私は考えてみた。何も言わない私の様子を感じ取ったのか、考え込んでいる姿でも想像したのか、あやこがまた、軽く声を立てて笑った。 「そう言えば誰かが「恋の味」って歌ってたねぇ?コーヒーは」 あんた実際飲みすぎて飽きてるんじゃないの?とあやこが冗談めかして言った。私は、そういうものでもないけどなぁと思いながら、そんな歌もあったね、とだけ返した。 結局お見合いは、ゆかこさんが話を持ち込んだ日から二週間後の日曜と決まった。相手は、妹と母が選んだ。なるべく顔のよさげな感じにしといたから、ハゲじゃないよと言うのがその妹の弁だ。 「広告代理店の営業さんだって。着てるものもまあまあだし、いいかもよ?」 「だったらあんたが見合いしたら?」 「だってまだ学生だもん。お姉様と違って四大生ですの」 言葉の後、何を思ったかみやこはオホホ、とわざとらしく笑った。この先二年くらいの間は、彼女のところにゆかこさんからそういう話しはやってこないだろう。うらやましい事だ。もっとも、二年後以降はどうだかわからないけれど。母は、樟脳くさいといけないからといそいそと、若かりし頃作った振袖をタンスの奥から引きずり出し、やっぱりきちんとしまってあるから悪くなってないわねぇと、独言のようにつぶやいた。母は「なんちゃってお嬢様」だ。三人兄弟(と言っても真ん中の人だけが男なのだが)で一人だけ歳のはなれた末っ子で、両親からだけではなく親戚一同からかわいがられた、といつか言っていた。それでその冷淡さは何だろうとも思うけれど、持ち物やら着るものは、そんなわけで一揃え、お嬢様のように持っていたと言う。もっとも、お古というのも多かったらしいが。特筆すべきは、和服の類だ。本人が好きだったから余計だろうが、我が家の母は、きれいにきちんと一揃え以上、着物だけは持っている。私の短大の卒業式には、袴だけなんとか手配して、後はすべて母の持ち物やら技術でクリアした。着付け代というのはなかなかどうして高いものなのだ。ちなみに矢絣は、ない。一生一度だし着てみたいなとは思ったのだけれど、あれは元々女中の着物だから、普通に作ったりはしないんだそうだ。今時そんなことを言うのも難だけれど……考えてみればあの手の格好はその時にしかしないわけだから、わざわざ作ると言うのも変か。 「一応防汚加工してはあるけど、汚さないように」 「……がんばります」 目の前に広げられた、成人式にはしぶ目だなぁと思われる振袖に向かい、私は言った。何に対して誓ってるんだか。そして、何をがんばるのやら。思いながら私はため息をついて、母に言った。 「お母さんも……お見合いだっけ?」 「そうよ」 「……これ着て?」 「そうよ。あんたのおばあちゃんが着物作ってあげるからしてくれ、って言うから、これ作ってもらって」 そうして見合い結婚した人の娘が、私か。しれっとした顔で言った母を見ず、私は、じゃあその見合い、最初はことわるつもりだったんだろうな、これだけ作らせて、と何気に思ったのだった。 そして私の人生最初の見合いは、ことわったにもかかわらず「もう一度会ってほしいそうなんだけど」というゆかこさんの言葉の後、その約束をせざるを得ない状況へと、転じていったのであった。 「男好きするタイプにも、ほどってものがあるんじゃないの?」 「……ほっといてよ」 いつものあやこの電話が、それを決定されてしまった直後にかかってきて、私は余計に疲れてしまった。あやこには悪いのだけれど。あやこはそれを悟ったのか、抵当なところで本当に切り上げなさいよ?でもどういう人か教えてね、とか言って電話をさっさと切ってしまった。最後の一言が余計だよ、と思いながら、私はひたすらため息をついた。そ、そりゃあね、自業自得なんだけどさ。きちんときっぱりことわればいいんだけどね。でも、それができてたら苦労なんてしないわ。そういう性分なんだし。いまさらながら私は「人当たりのいい」「愛想のいい」凡庸な娘さんをやってきたことを後悔した。でも、普通の女の子は普通の幸せが一番幸せなんじゃないか、とも思う。そこはそれ、人それぞれなのだけれども。 「お見合い、ですかぁ?」 そして、気が滅入っている時にはろくなことがないわけで。その日ファックスの誤送信をやらかして上司に注意された私は、最近元気ないですね、という後輩の言葉に、とうとうぽろっと言ってしまったのだった。お昼休みの人気のない事務所で、私と彼女はおやつだかデザートだか、と言った感じのクッキーをつまみながら、言ってみれば世間話に興じていた。 「松川さん、そういうのするんだぁ」 三つ年下の小綺麗、という形容が似合いそうな彼女、園山さんはつぶらな瞳をぱちくりさせてそう言った。私は笑いながら困った顔をして、 「伯母さんのすすめで、仕方なく、だけどね」 「でもお見合いでしょ?そんなに困っちゃう事ですかぁ?」 小首を傾げて、まるでリスのような表情で問い掛けられて、私はたはは、と少しだけ笑った。 「したくてしたわけじゃないから。今のところ結婚する気もないし」 「そうなんだ……でも、仕事に生きる人、には見えないですよぉ?」 おっとりのんびりに聞こえる口調で、彼女はわりとはっきりものを言う人だった。確かに私も仕事に生きる人ではないし、それを装ったことは一度としてない。だから言われて当然だけど、それでも、それじゃあ他に何にもないみたいに聞こえて、いやな感じ。 「松川さん、このお仕事、好きですかぁ?」 「うーん……嫌い、ではないけど……」 「じゃあ、結婚するとなったら、いずれ辞めちゃいます?」 「ど……どうかなぁ……」 とりあえず私はそこを笑ってごまかした。園山さんは少し考えるような顔をして、 「人それぞれだからいいんですけど、会社辞める口実に結婚、ていうの、アリですか?」 「ど……どうだろう、ねぇ……」 「何かそれってー……ちょっと卑怯じゃありません?」 「……はい?」 別に、辞める口実に結婚を持ち出してお見合いしてるわけじゃないのだけれど。言えず、私はそんなふうに問い返してみた。とりあえず、今のところ働くのをやめようとは思ってないけれど、彼女はそういうふうには、どうやら解釈していないようだった。 「会社がいやなら、会社がいやってちゃんと言って辞めればいいんですよ。違います?」 「……そうねぇ」 もしかして説教かしら、と、私は何となく思った。それとも、私のこと嫌いなのかしら。前にもなんだかんだとブツブツ言ってたし。神妙な目が、ちょっと恐かった。 「では!ひなちゃんのお見合い二回目……デート?まあいいや、男性遍歴の終止符を願って!」 「ちょっと待て。何?それは」 最近パソコンの作業はどう?と言って、カヅユキがうちに顔を出したのは、その見合い相手と二度目の顔合せの直前のことだった。いろいろあって全然進んでないから手伝え、と言うと、そんなの一緒についてるソフトで簡単にできるよ、とか言われて、言われながらやっていたその時、みやこがお茶を持って現れたのが運の尽きだった。そろそろ蒸し暑いからと言って作られ始めた麦茶は冷えていて、グラスはあっという間に汗をかいた。 「かんぱーい!」 みやこが声を上げると、会わせてカヅユキもグラスを持ち上げた。麦茶で乾杯なんかして楽しいんだろうか、この人達は。私はそう思いながら、パソコンの画面を見てそちらに集中しているふりをした。 「とうとうひなちゃんも観念したか。で、どんなヤツ?相手」 一人、カヅユキは盛り上がっているらしい。それにつきあっているみやこはそれより少々大人しかった。 「三十一才、某広告代理店営業主任、だって」 「へーえ、三十一歳会社員。手応えのほどは?」 手応えのほど、と言われても。答えることは何もなかった。何と言うか、絵に描いたようなお見合いで、簡単な自己紹介が終わると二人にされて、二時間もつらつら話したかと思うと、じゃあ連絡は後ほど、という具合にゆかこさんが仕切ってしまって……後は想像に難くない感じ。適当にお話して、愛想笑いで答えて(だってむっつりしているわけにはいかないし)……そのまま、何だかずるずると幕引き……私はことわったのに、今回の話はなかったことに、と言ったはずなのに……その言い方だとまずかったのかもしれないけれど。画面を見ながら、キーボードやマウスを操作する手を止めて、私はため息をついた。二人は私が答えないのを見て、 「おねぇ、手応えのほどは?って、カヅ君が」 「人が聞いてやってるんだから、そのくらい教えろよ」 「……ことわったつもりだったのに」 ち、と、はしたなく舌打ちしてから私は言った。こういう時の私の機嫌がどういったものかよく知っているはずの二人は、知っているから他人事なのかもしれないけれど、口々に言った。 「それはそれは、ご愁傷様で」 「日本人の悪いところだねぇ。イエスノーはっきりさせないから」 「いや……この人の場合、日本人だっていうのは当てはまらないかもね」 言ってろ。胸中でつぶやき、私は自分でもわかるくらいの苦虫をかみ潰したような顔で、また、ちっ、と舌打ちした。全く、はしたないことこの上ない。そういった形での出会いを望んでいる女の子にしてみれば、割合条件のいい相手、というのは本当のところだったけれど。 三十一才、会社員、営業の主任。細かいことはゆかこさんが聞いてくれたり説明してくれたりで一通り耳に入っては来たけれど、それは鼓膜をゆらしただけで、頭の方へは響いてこなかった。その年齢で主任というのは、その会社ではどうなんだろうと思いつつ、とりあえず私は見合いを半ば放棄していた。ホテルのロビーのカフェで繰り広げられたその奇妙な会合(?)の間、私は注文した抹茶と干菓子のセットに御執心だった。仮面の下では。そのホテルの喫茶は和風テイストが好きらしく、紅茶、コーヒーは適当なメニューだったにもかかわらず、煎茶、抹茶が数種類と、日替り和菓子のセットなんかがあって、私の心はそんなところでちょっと小踊りしていた。その影響で二人にされた時にやや機嫌が良かったのは、結果としてまずかったけれど。とりあえず趣味の話をして、最近こっていることは、と聞かれて喫茶店めぐり、と答えてしまい、変な顔をされるかと思ったら、さすがは営業と言うべきか、相手は上手くへぇ、めぐるんですか。最近増えてますよね、とか何とか切り返してきて、話が続いてしまった。ああ、話が続いてまずいと思わない、私の浅はかさよ。誰だって自分の好きなものがほめられたりしたら、喜んでしまう事だろうが、この場合の私はそういう愚行に走ってはいけなかったのだ。だってことわる見合いの相手とにこやかにお話、よ?まずいでしょ、それは。とにもかくにもそんなわけで、言うなればやや上手く乗せられて、私たちの話は弾んでしまった。ただトドメに「デジカメ持って写真とったりして、チェックしてるんですぅ」とマニア臭いところをアピールしたから、大丈夫だろうと思ったのだけれども。それもどうやら裏目だったようだ。ゆかこさんいわく、 「初めての方なのにお話も弾んで、いい感じね」 しかし彼女が私の「とっかえひっかえ」を知ったら、どうなることだろう。正確にはそうじゃないけど、その事実はもしかしたら本当は、とても使えるのかもしれない。でもそんなことに後から気付いたって遅いのだ。 「おー、いい感じにできてるじゃないの」 パソコンが面に向かう私の背中越しに、作りかけのページを見ながら妹が言った。カヅユキはその妹の背中越しに、 「今時はいいソフトがあるから、そのくらいなら訳なくできちゃうって。みやちゃんもやったら?」 いちいち腹の立つことを言うヤツだ、と口に出さずに私は思った。 「松川ちゃん、お見合いしたんだって?」 さて、ぽろっと言ってしまえば、翌日からそういった話題は会社中に蔓延するわけで、しかしそれはちょっと時間差で私を襲ってきたりした。その見合いが「いい感じ」に進むことは私にとってはあんまり嬉しくなかったけれど、くよくよ考えていても埒が明かないということは身に染みてわかったので、考えるのをやめた。けれどそういった襲来があろうという予測は、簡単につこうと言うものだ。だからその辺りにだけ、私は心の準備をした。時間差で助かった、そんな感じかしら。外注の運送業者の運転手に言われた時にはちょっとびっくりしたが、そこはそれ、愛想がいいのが私である。 「えー、青送さん、どうして知ってるんですかぁ?」 青山運送、略して青送の運転手は、出荷の誰々から聞いた、オレも松川ちゃん狙ってたのになあ、と冗談めかして言った。妻子持ちに言われても信じられないなぁ、とか言って返しながら、しばらくはこういう質問責めだろうなと仮面の下で考える私がいて、何だかちょっと楽しかった。う、裏表激しい、のかな。愛想笑いは確かにお勤めを始めてから上手くなったけれど、元々人と話すことは嫌いではないし、知らない人でも不快にはさせたくないからにこにこしている。もしかしてそれはいわゆる「腹芸」なのかしら。こびているつもりは全くない。証拠に、女性の諸先輩方にもすごく嫌われているということは……あったっけ?知らないだけかもしれないけど。不服があれば申し立てるし、でも、そういうときに限って語尾がいい加減なのも確か。これが大人になるということ?我慢をするということ?とかいう禅問答はさておき……いいじゃない、笑って過ごせる話題なら、笑ってすませれば。私はやや投げやりだった。人のプライベートに口出さないでください、とか言いませんようにと、自分で自分に願ってみたりもした。だって見合いしたのは事実だし、また会う羽目になってるし。本当のことだもの、変に否定しない方がいいに決まっている。でも、 「じゃあ結婚退職?寿だ?」 というのは、全く考えていないから、否定したりするわけなんだけど。伯母に勧められて仕方なくですよ、と言えば、似たような経験のある先輩は(男性で数人)大抵同情し、パートの先輩方は(既婚者。時々母の知人)でもそろそろじゃないの、と、冷やかしとも皮肉とも取れない言葉をおまけにくれたりする。そしてそれは結構ぐっさりと、体のどこかにつきささったりするものなのだ。でも、気にしていたらまた仕事に支障が出る。大人の女なんだから、些細なことでぐらぐらせずに、しっかりしてなきゃいけません。第一、ことわる話なんだから。それに、騒がれるのもせいぜい一週間くらいでしょうよ。その頃には今度こそ決着だってついているに違いないわ!しかし、そう上手く問屋が卸してくれないことも、世の中ざらにあったりするわけで。 「あちらさんがね、どうしてももう一度会ってお話したいって仰るのよ」 野沢ゼンノスケ、というのがその人の名前だった。古風ですね、と何気に言ったとき、つけたの祖父なんですよ、と、その人は笑って答えた。彼は礼儀正しく、見合いの席なんだからそれは当然のことかもしれないけれど、私に直接連絡先を教えず、聞かず、それらの伝達はすべて仲人であるゆかこさんと、あちらの、やはりおば様という方に委ねられていた。それって……どこかで歪んだりしないのだろうか。ゆかこさんからかかってきた電話をとって、私はそんな思いに至った。 「ひなこちゃんいいこだから、よっぽど気に入られたのね。私も鼻が高いわ」 「ゆかこさん、あの……」 「それでね、いつがご都合よろしいですか、って」 何にもよろしくないってば。私は思った。言おうと思った。でも言えなかった。あああ、と、口もとで小さくうめくと、あら何、と気付いてゆかこさんが言った。 「体の具合でも悪いの?」 そういう気はよくつく、いい人なんだけどなぁ。多分親友あやこに言わせれば「なんちゃってややボケ」わざとちょっとだけとぼけた人、という分類がされることだろう。そんなことはないけど、と言って、私は仕切り直すことにした。 「ゆかこさん、あのね」 「それでね、あちらの奥様に、できたら一両日中に連絡がほしいって言われて。ゼンノスケさん、明後日から出張なんですって。大変よねぇ」 そして私はまたしても、この人のペースに巻き込まれてしまうのだった。な、情けない。思いながら、結局私はそこでばっさりと、その話を一刀両断するがごとくには、終わらせられないのであった。約束だけを一方的に取り付けられてしまって、じゃあまた何か会ったら電話頂戴ね、と言った彼女に、それでも一言だけ、 「私、まだ結婚する気、ないから」 「あら、すぐに、なんて言わないわよ。一生問題だもの。だから今はじっくり……そうね、お試し期間だと思って楽しみなさいな」 うふふ、と、歳に似合わないかわいらしい声でゆかこさんは笑った。私は、真意が全く伝わっていないことを感じながら電話を切り、その場で一人ため息をついたのだった。 あやこが次の休日私をつれて行ったのは「サンディ・クローズ」という名の、某人形アニメ映画をモチーフにした個人経営の喫茶店だった。おもしろいところ知ってるでしょう、と鼻高々であやこは言い、ハロウィンとクリスマスはもっとおもしろいわよ、と付け加えた。それはどちらかと言うと今時流行りのカフェではなく、その映画の世界観やキャラクターが好きな人のための、とてもマニアックな空間だったのだけれど、知らない人が見てもかわいらしい内装やこったデザインのメニューで、私の心も一発で仕留めてしまっていた。惜しむらくは突然の呼び出しで、デジカメもノートも持って来ていないことだろうか。 「よく知ってるね……てゆーか……かわいいお店ね」 「でしょ。ちょっとは見直した?」 そこはいつも私たちがうろついている市街ではなくて、郊外の、ちょっとしたドライブのコースの途中にあった。マスターがこの映画が大好きで、その作家さんが大好きで、思い余って始めたらしいそのお店は、甘味のボリュームと味に定評があって、この辺りではちょっと有名らしかった。 「この内装で小豆ってところもツボかなぁ」 やや大きめの器で出されたクリームぜんざいを食べながら店内を見回し、あちこちにぶら下がったキャラクターの人形やタペストリーを眺めていると、でしょ、そうでしょ、とうれしそうにあやこが言った。目の前にはホットのグリーンティーとアメリカンサイズのチョコレートケーキとがあって、アンバランスと言えばそうだったけれど。 「近くに日帰りできる温泉があって、お歳を召したお客さんが多いからこういうメニューなんだって。ねー?マスター」 珍しくカウンターの席につかされた私は、ここへ来てその理由に合点がいった。あやこは、どうやらここをよく知っているらしい。マスターはそのカウンターの中でにこにこしながら、はいこれサービス、と言ってコーヒーのおつまみの小皿に、海苔巻きのあられをのせて出してくれた。何か、変な感じ。 「そう言えば、見たよ?ホームページ」 帰りに温泉にいこうね、と言った後のあやこはテンションが高めだった。私がカフェフリークなら、彼女は温泉フリークとでも言うところか。 「素人の作ったわりに結構立派でびっくりしたよ。あんたセンス良かったんだねぇ」 「それはほめてるわけ?それとも単純に驚いてるわけ?」 「うーん……後者かな」 あはは、とあやこは笑った。よく考えなくてもこうやって彼女と会って話すのは久しぶりで、ちょっとの間にいろいろあった私は、それだけで何だか気分が楽になれた。だからこの際彼女のそういう口の聞き方には目をつぶることにした。何と言っても、つきあい、長いですから。 「あたしもパソコン本格的にやろうかなぁ。今やってるのメールくらいだし。あーでも……特に目的もないなぁ。メール以外」 「ホームページでも作ったら?「温泉バカ一代」とか言って」 「やぁね、あんたと一緒にしないでよ。そんなにフリークじゃないもん」 「どうだか」 あやこは、多趣味と言えば多趣味だ。昔からいろいろなことに興味を持っていて、いろいろなことに首を突っ込みたがる。テレビもよく見るし映画もよく見るし、何だか難しい政治の話なんかも私にくらべたらよく知っている。定職について一つのことを完遂できないのが欠点と言えばそうだけれど、そういう自由な彼女を一つのことに縛り付けるのもどうか、という感じ。最近どう、と問いかけると、私の知らないいろいろがくり広げられて楽しい反面、つきあいが長いためか厳しい言葉も多い。でも彼女になら、こちらから多少の反撃をしてもあんまり支障はないから、まあいいとして。 「そう言えば、この近辺の憑き物落とし屋リストが手に入ったから、落とすときは一緒に……」 「行かないってば、そんなところ」 イヒヒ、と楽しそうに笑う(女の子がイヒヒ、は問題だけど)彼女にばっさり言い返して、私もくすくすと少し笑った。 「ああそう言えば、見合いどうなった?」 そしてそんな会話の終に、その話題はこぼれるようにポロリと現われた。私はすっかり大きなクリームぜんざいを食べ終わっていて、口を動かさない口実をちょっとだけ探して、それがないことに気付いてため息をついた。 「……どうもこうも」 「上手くいってるんだ?じゃあ」 「……上手くって言うか……ねぇ……」 言葉を濁してから、私は深呼吸をして、今までの経緯や現在の状況を話して聞かせた。すっかり聞き終えたあやこは、ふーん、と言って黙り込み、それから改めて言った。 「そりゃあ、あんたが悪いわ」 うう、きついお言葉。閉口して、胸の中だけで私は言った。本当に仰る通り、で、返す言葉もない。 「で、でもね……結婚する気はないって、ちゃんと言ってあるんだけど……」 「言ってあるんだけどまた会うわけでしょ?それって、結果そうなったら大成功じゃないのよ?」 「……そうだけど」 「あんたの愛想いいのは美点だけど、ものはっきりことわれないのは最大の欠点よ?」 言われると、弱い。どうしてあの母の娘でこうなんだろうとか、思うときりがない。自己嫌悪の嵐、というヤツだ。なまじ外面がいいと、こういう苦労は否めない……でも外面が良くないと、支障はいろいろあるのだから仕方がない……とか言ったらまた、怒られることだろう、あやこに。あやこはしょうがないな、とため息をついた。そしてそれから苦笑を漏らし、 「ま、優しいのは、あんたの一番いいところだから……しょうがないかもね」 「そ……そうかなぁ……」 「悪く言うと優柔不断だけど」 ぐさっ、言葉が刺さった。痛い。まぁこれはあんたの問題なんだから、自分でどうにかしなさい、と最後にあやこは軽く言った。 「まぁでもそんなストレスなんて、温泉にでも入ったらぱぁーっと吹き飛んじゃうって!」 「そ……そういう問題?」 結局そこか、と私は言いたい気分だった。しかし温泉のことになるとあやこの目の色は違っていて、何を言っても聞いてくれなさそうな、そんな感じだった。 そしてまた、最近どうよ、と言ってカヅユキがうちにやってきたのは、その翌日だった。学生はひまでいいわね、悩みもなさげで、と言ってやると、ヤツはあっさり、まあね、とか答えた。 「それにしたって最近来すぎじゃない?またお父さんと喧嘩してるの?」 カヅユキとは、あやこより三倍以上もつきあいが長い。何しろほんの小さな子供の頃からだから、本当に長い。半分家族みたいなものだし。だから一応、彼の家庭の事情と言うのにも、我が家は総出で(?)通じていた。彼とは血縁という意味では全く繋がりがない親戚の我が家に、それでもよく遊びに来ていた。彼の父親、私の伯父さんという人は母より十五も歳が上で、頭には白いものが混じって、すでにごましおの状態だ。子持ちの人と結婚して、その子供が中学生になるまで特別に支障もなく家族をやってこられた、というのは、最近の世の中をぐるっと見回してみると、なかなかできた人だと思えるのだけれど、カヅユキが長い反抗期に入ってしまって以来その状況の打開はできていないから……そんなにできた人でもないのかもしれない。 「そういうんじゃないよ。近所に来るのが多いだけ」 皮肉めいた私の言葉に彼はそう答えて軽く笑い、笑った後でふう、と息をついた。彼がうろうろしているのは我が家の居間か私の部屋だった。ちびの頃によく泊まりに来ていたから、その名残りもあるんだろう。ついでに言うと、この頃では私のパソコンの先生でもある。ちょうどよかった、ここ教えて、と言って私は彼を画面の前に座らせて、クリアしなければならない問題にとっかかりはじめた。キーの配列がわかっててマウスが使えてアルファベットが読めれば大丈夫だよ、と彼に言われてはじめたこの遊びは、しかしそう上手くもいってくれず、パソコンなんて仕事以外にさわらない人種だった私はいまだに四苦八苦していたりする。大体、クリックする位置がドット一個分しか違わないのに出てくる絵が違うってどういうことだ!と言うと、しょうがないだろ、繊細なんだから、誰かさんと違って、とカヅユキはいやみったらしく笑ったりしたものだった。どうせ私は精密機械みたく繊細じゃないですよーだ。 「ひなちゃん、カメラの使い方上手くなってるじゃん。関心関心」 そうして一連の作業が終わると、珍しくカヅがその画像を見てそんなふうに言った。私はちょっとうれしかった反面、 「何?また悩み事?」 「またって……オレは素直にほめてるんでしょ?どうしてひねくれた見方するかな……」 「だって最近誰もほめてくれないし……口実作ってここに来るのは昔から得意じゃない、あんた」 自分で言っていて寂しい言葉を吐き出すと、カヅはうん、ちょっとね、と言ってそのまま口ごもった。二十四にもなるのに、相変わらず彼はまだ反抗期で、良く言えば感じやすく、悪く言えばとても脆かった。 「実は……相談があるんだ」 「相談?」 どうせまたお父さんともめた、とか、お母さんが泣いた、とか、そんな話だろうなと思っていた私は(十年も見ていればさすがに慣れる)驚きもせずにそんな彼を見ていたが、次の一言で叫ばざるを得ないほど、驚いたのだった。 「一日だけ、フィアンセやってくんない?」 けれど私は叫ばずに、逆に言葉を失っていた。絶句する私の目の前で、てへ、とか言ってカヅは笑った。 頭の痛い話は、それから二十分ほどその場でくり広げられた。ある女の子に結婚を迫られている。何度だめだと言っても聞いてくれない。だから婚約者のフリをして協力してくれ、と、要約するとこんな感じだろうか。その女の子というのは大学の同期で今はOLをしていて、その頃にはうまくいっていたのだが向こうが就職してからは歯車がずれたようになってしまい……以下略。何と言おうか、ばかばかしくて聞く気にもなれないような、ありがちのアクシデントだった。 「だからって、どうして私なのよ?みやこに頼んだらどうなのよ?」 「みやちゃん?みやちゃんじゃ説得力がないよ。まだ学生だし」 「あんただってまだ学生でしょ。いいじゃないの、だったら」 「年齢的にもひなちゃんのほうが説得力があるし。ねぇ頼むよ、こんなこと頼めるの、ひなちゃんくらいしかいないんだからさぁ?」 返す言葉もなかった。そりゃあ、二十歳の女の子より、プラス五歳くらいのほうが説得力はあるわよ。けれど、だからってどうして私がそんなことに加担しなきゃならないのだろうか。思う私の目の前で、カヅユキは両手を会わせて頭を下げていた。お願いします、拝んじゃうよ、ただとは言わないから、と、お正月の初詣でより殊勝な態度で、端から見ていると痛々しいほどだった。しかし、同情の余地はない。ないと言ったらない。ないはず、なのだが。 「……どうしてこういうことに……」 その週の金曜の夜、私は彼にフレンチをおごらせる約束をさせて、フレンチレストランに入ることのできるスーツで、カヅユキと待ち合わせをすることにした。結局、というべきか。頼み込まれるとことわれない性格はあだにしかならなかった。しょうがないなぁ、と小声で漏らすと、カヅユキは裁判で逆転した被告側のようによろこんで飛び上がり、私の手を取ってありがとう、恩に着る、と言ってぶんぶんそれを振り回した。どのみちフリをするだけだし、ただとは言わせずにすみそうだし、また見合いの時のように腹をくくって私はその待ち合わせの場所に向かっていた。もし話がこじれてややこしいことになったら高いワインだっておごらせてやる、百グラム数千円の紅茶を買わせてやる。もうそう思うしかなかった。諦め上手なのかも知れないが、それで納得するのは何だか嫌だったので、とにかくこれはビジネスなのよ、取り引きなのよと自分に言い聞かせ、いつもより飛び切り愛想良く、かわいらしく、努めることにした……何だかちょっとこれって、哀しいかもしれないけど。ついでに言うとこのために午後から半休までとったりした。ちょっとイトコに相談があるって言われて、深刻なんですぅ、とややわざとらしく言うと、何故か会社の皆様は変に納得してくれて、特別追求されずにすみそうだった。その辺は私の役得なのかもしれない。あやこに話したらなんて言うだろう。それがおいしいところよ、とか言って諭してくれるんだろうか。 「ひなちゃん、ごめーん!」 約束の時間から十五分後、あわてた様子でカヅユキがようやく姿を現した。比較的かわいらしいスーツとは裏腹に、とんでもなくむくれた顔をしていた私は、見つけるなり開口一番言い放った。 「遅い」 「ちょっとバタバタしてて出るの遅くなっちゃってさぁ。悪い悪い」 いつものように軽い調子でカヅユキは言った。悪いと思っている顔にはとうてい見えず、私は更に眉をしかめる。そして、そのあんまりにもラフな姿に対して私は更にいちゃもんをつけた。 「何、そのくたびれたなりは。今日フレンチじゃなかったの?」 「え?今日?何言ってんの?」 「ただで働かせるつもりじゃないでしょうねぇ?カヅユキ君?」 ぱん、と、一歩踏み出したヒールの底がコンクリートの上で小気味好い音を立てた。さしものカヅユキもこれには怯み、ほぼ同時に微かに後退する。 「ひ……ひなちゃん……恐いよ?」 「そうかしら。いつもと変わらないわよ?」 「ふ……フレンチはぁ……また今度おごるよ。俺学生だよ?そんなにとんとん金なんて用意できないよ?」 「じゃあ積み立てることね。いい?高く着くから!」 普段より強気で言ってやると、カヅユキは萎縮して、はい、善処します、と答えた。確かに彼は貧乏だ。私も、貧乏学生を揺するつもりはない。そんなに悪人じゃないもの。どちらかと言ったら善人よね。嫌々ながらも彼を助けてやろうっていうんだもの。私は自分に言い聞かせるように胸の内で思い、大きく一つため息をついた。カヅユキはその隙にいつもの軽い笑顔に戻り、 「とりあえず、いこーか。彼女、この先の喫茶店で待ってるんだ」 「この先……どこよ?」 喫茶店、と聞いて私も、ややそちらに興味が移る。ほっとしたのか、カヅユキの口調は更に軽く、そして滑らかになった。 「知ってると思うよ?「ラ・ムーファ」って酒も飲めるとこ」 そんなわけで実はこの日初めて、私はその「ラ・ムーファ」に、お酒の飲める時間帯に足を運んだのだった。 キャミソールドレスに白のカーディガン、という最近では定番っぽいスタイルの、小柄できれいな女の子を目の前に、カヅユキがこの人だよ、と言うのを聞きながら、私はどうも、と軽く会釈をした。怪訝そうな目が私を睨んでいて、何だかここからが戦いの始まり、という感覚で……ちょっと恐い。四人がけのテーブルで、私はその彼女の真正面に座らされ、カヅユキはいつものようにへらへらっと笑いながら、やだなあそんな恐い顔で、と言った。恐い顔もするだろうな、と思った私はちらりと、のんきと言うか何も考えていなさげな彼を見る。彼はそのまま彼女に私を紹介し、私に彼女を紹介し、あれ、まだ何も頼んでないんだ、お腹すかない?とまた軽く言った。山名みずき、というその人は、多分笑ったりしたらそれなりにかわいらしいのだろうが、眉間にはしわが寄りっぱなしで、眉はずっと釣り上がっていて、視線だけで私をぎゅうぎゅうと締め付けるようにこちらを見ていた。ひなちゃん、何頼む?とのんきに言ったカヅユキの小耳に、あんたが払うのよ、と言ってから、私はいつもの定番の特大パフェを頼み、来るまでさぁどうしていようと考えた、が。 「松川さんは、カヅユキとはどのくらいのおつきあいなんですか?」 握り拳をテーブルの上に置いた格好の彼女が、まずそう口火を切った。あちらにしてみれば、今から命まで賭けられるような決戦が始まるのだから、無理もないと言えばそうだった。私はカヅユキをちらりと見やり、カヅユキは困った顔で笑いながら、 「あ……えーと、いつごろからだっけ。ねぇ?」 「生まれた直後じゃないの?」 しらっと、私は言った。ぴくん、と、彼女の頬がひくつく。変な汗でもわきの下にかき始めているようなカヅユキは、あー、そうだっけ、と小声で言って、母は、と乾いた笑い声を漏らした。 「え、えーとね、みずき。ひなちゃんは……イトコなんだよ、一応」 「血は全然つながってないけどね」 私は、彼の味方なのかそうでないのか自分でもよくわからなかった。この場でふりまく愛想も、この男に対する優しさも、ないと言えばそうだった。いつもなら適当に話を合わせてあげたりなんかするのだが、極端なことを言えば私はここにいさえすればいいのだ。とりあえずおいしいお茶の出てくるカフェバーにいるわけだし、飲めるものも食べられるものもせしめられるだけせしめてやろう。そんな気分だった。彼女は一度だけじろりとカヅユキをにらみつけた。そしてまた、私に言った。 「婚約なさったって聞いてるんですけど、いつごろ?」 「いつだったかしら」 「や……やだなぁ、俺が二十歳の時にはもう決めてたじゃない」 焦りまくりながらそんな言葉が吐き出される。よくも言えたものだと思いながら、私はため息をついた。そして、 「じゃあ……じゃあ最初から私とは遊びだったって言うの?」 出るべき言葉がそこに出てきた。確か彼女とは、彼女がまだ大学生だった頃に知り合って付き合っていた、と言っていたから、彼女の中では脈絡的にそうなるわけで、当然の怒りと言えば当然だった。ああ、何だかあほらしくなってきた。どうして私が、こんなヤツのためにこんなことしていなきゃならないんだろう。そう思っている矢先にようやくテーブルに特大パフェが運ばれてきた。甘いものでも食べて気を紛らわせなくっちゃ。手を伸ばしながら、ちらりと視線を彼女の前に投げる。一杯のコーヒーを見つけた直後偶然彼女と目があった。相変わらずこちらを睨む目は、何を思ったか突然ウェイトレスを探し始め、 「私にもこれと同じものください!」 赤く塗られた唇は、その直後言い放った。驚いたのは私だった。こ、これって、明らかに私と張ろうとしてるわよね。思いながらも私は遠慮なく、長いスプーンで掘り進むようにパフェを食べ続け、しながら、どうするのよ、と視線だけでカヅユキに問いかけてみた。カヅユキは困り果てた顔で必死に笑いながら、 「お……女の子って、甘いもの、好きだよね……あはは」 もうどうにもできないような顔で言って、自分で頼んだコーヒーに口をつけたのだった。 |